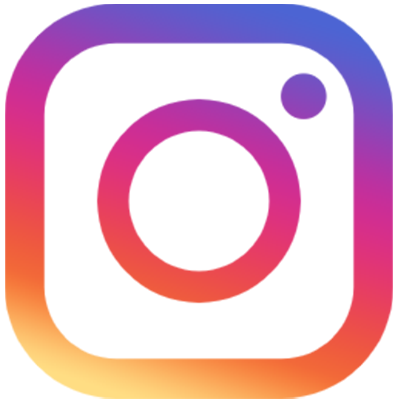毎月23日は小説の日!【ブルックリンブラザーズ(前編)】
昔、ブルックリンの映画館で観た映画を思い出す。
「ニューヨーク州には隠されたもう一つの区がある」
そんな謎めいた言葉を手がかりに冒険をする二時間くらいの話だった。
ハイスクールの学生であるニッキーの頭に、その映画の思い出がよぎった。今は地理の授業中で、ニューヨーク州の成り立ちについて説明が続いていた。
しかし、ニッキーの意識はすっかりとその映画の思い出に傾いていた。
親子愛をテーマにしたハートフルなドラマで、ニッキーは二十回程泣いた。あまりにも泣きすぎたので、隣に座っていた老紳士が驚き、「そこまで手に汗握る映画だったかね?」と聞いてきたものだった。ニッキーの流した涙は顔全体を濡らし、それを老紳士は汗と勘違いしたのだろう。
(映画のタイトルは確か)
教科書に目を落として思い出そうとする。
だが、うまく皮の剥がれないチキンのように、もがいても記憶は取り出せなかった。
授業の終わりの時間を教室の時計で確かめると、残り五分ほどだった。
映画を見て過ごす五分は一瞬のようだが、退屈な授業での五分は永遠に感じる。
あと五分耐えれば今日の授業は全て終わり、自由の身になれる。
そんな風に考えていると、遠くから深く響く音がした。
二度、三度と地面が震えるような轟音。
そして、ガラスが何枚も割れる音が続いて聞こえてきた。
気づけばニッキーは教室から飛び出していた。クラスメートたちも同じだった。先生が制止する声も届かず、ニッキーたちは一緒になって音の方へと向かっていく。
途中で他のクラスの生徒たちとも合流し、大きな集団となった。
音がしたのは図書室からだったらしい。
(テロでもあったか? だとしたら、早く外に逃げなきゃいけない。いや……こういう時に慌てて外に出た時を狙って、テロリストは本命の爆弾を仕掛けていたりするんだ。こっちは囮だってな。映画で見たぞ)
ニッキーの予想は外れた。起こっていたのはテロではない。
既に近くの教室から生徒たちが集まっていて、その人混みの間からニッキーは図書室の方を覗いた。
扉から本棚が倒れるようにして飛び出している。周囲はガラス片ばかりだった。
図書室からは、壊れた扉をくぐって生徒たちが出てくる。周囲の人たちに手助けをされて、ある者は泣きながら、ある者は激怒しながら救出されていく。
被害に遭っていたのは後輩である二年生の生徒たちだった。図書室から出てきた彼らは口々に「本棚が倒れてきやがったんだ。順番に全部倒れたんだぜ。俺は生きてるのか? 生きてるよな!」と事情を聞きに来た教師に喚いていた。
誰もが入口の割れたガラスで制服が傷ついており、一目で被害者かどうかの見分けはついた。
その内の一人、やたらと教師に状況を説明する生徒がいた。
その肌の黒い男子生徒には見覚えがあった。ニッキーの弟の友人、ゴルゴだ。
ニッキーと彼は弟を通じて話をする仲だったので、知らない顔という訳ではない。事情を聞けるかもしれないと歩み寄って「無事なのか、何があったのか」と声をかけてみた。
「ニッキー・マークス! ニッキー! やべえんだよ。こいつはダイハードの撮影じゃねえ。分かってやがるのか」
「分かってるさ。ダイハードだったら学校ごと吹っ飛んでるぜ」
ゴルゴは興奮した様子でニッキーの肩を叩くと、窓の破損した図書室を見るようにジェスチャーで促していた。
「棚がいきなりドミノみたいに崩れてきやがったんだぜ。本棚の間にいた奴ら、どうなったんだ」
それから、額から血を流している生徒や、抱き合って泣いている生徒たちで廊下は騒然としてきた。
立ち尽くしてその様子を眺めていたニッキーだったが、ふとある事に気づいた。
弟の友人であるゴルゴがここにいる。恐らくは授業で図書室を使っていたのだろう。今、丁度終わりのチャイムが鳴った。ということは、ゴルゴのクラスの生徒たちは皆、この中にいたことになる。
ニッキーの弟のラルフもこの事故に巻き込まれた……。
ゆっくりと図書室の方へと足が向かっていた。
中から誰かの叫び声が聞こえてくる。
「下敷きになってるやつがいる! 引っ張り出してやってくれ! 血が出てるんだ! やべえぞ。誰か救急にコールをしてくれ、頼む!」
誰かが負傷している。
その報告からニッキーは「弟に限ってそんな」という現実から目を背ける考えと、「被害にあったのは弟に違いない」という思い込みとが混沌と駆け巡っていた。
パニックを起こしかけて、現場をうろついている時だった。
急に肩を叩かれた。
急いで振り返ると、ニッキーの前には見慣れた顔があった。
「兄貴、ここで俺が死ぬなんて映画みたいなこと、起こりはしないぞ。何だよ、そんな亡霊にでも会ったような顔してよ」
兄の心配などよそに、ニッキーの弟のラルフは苦笑して立っていた。
イングランドのサッカー選手、デヴィッド・ベッカムのように髪の毛を真ん中だけ軽く立たせた金髪。角張った頬骨から強面の印象を与えるが、兄に向けて笑いかけるその表情にはあどけなさが残る。そんなラルフは学校指定のポロシャツの裾が少し破れていたが、あとはまるで無傷であった。
ニッキーはラルフの無事を知って安堵のため息をつきそうになるが、強がってそれを抑え、咳払いで誤魔化した。
「心配なんかしてねえよ。お前はダイハードに出てもプラトーンに出てもプライベートライアンに出ても絶対にくたばらねえだろうぜ」
するとラルフは聞こえるか聞こえないかの声で笑い声を上げてから、騒ぎになっている図書室を振り返った。
「いきなり倒れてきてよ。俺も間一髪だったんだぜ、兄貴。しかしよ、これは……」
ラルフは言い淀んだ。そして、連絡を受けて駆けつけた救急隊員が、生徒たちの無事を大声で確認し始めた。
そこから一歩離れた場所にニッキーとラルフは立っていた。ようやく心が落ち着いてきたのだが、ラルフがぞっとするほど暗いトーンの声でニッキーにだけ聞こえるように囁く。
「誰かが本棚を倒した。こんなことが普通に起こるとは思えない。なあ、信じるだろ、兄貴」
同意を求めるラルフのその目は、まるで映画の中の登場人物のように演技じみているが、必死さが伝わってくるものがあった。
その時のニッキーは肯定も否定もしなかった。
弟が無事だったという安堵感に浸って、それ以外のことは考えられなかった。
遠くからゴルゴがやって来てラルフと抱き合い、お互いの無事を確かめ合い、当時の状況についてを話し始めていた。
ゴルゴは救急隊員にもらったのか、オレンジ色のタオルを肩から被っている。彼らの会話の中に入らなかったニッキーは、突然起こった耳鳴りに悩まされながら立ち尽くすしかなかった。
やがて、タオルに包まれた何人かの生徒たちが図書室から隊員たちに背負われて出てくる。自力では歩けないのだろう。その事実がニッキーをさらに恐怖の中へと突き落とした。
突然発生したその出来事はネットニュースになった。州の新聞記者も学校に来て取材をし、一度だけ地方のテレビ局がニュースのためにカメラを回しに来た。
それだけの騒ぎになったのは、この一件で死者が出てしまったからだった。
不幸にも亡くなったのはエリス・キンブリーという女子学生。
ラルフとその友人のゴルゴの同級生だった。
ニッキーはネットニュースで知ったのだが、彼女は本棚の下敷きになってしまったらしい。倒れた書架は全部で十だ。その真ん中辺りの六つ目あたりで巻き込まれたと書かれていた。
フェイスブックを覗くとエリスの死を悼む同級生達のコミュニティが出来上がっており、様々な追悼の言葉が並んでいた。
「目立たない性格だったけれど気が利いて親切で明るい良い子だった。将来は物理の先生になりたいと言って勉強を頑張っていた」
「家は貧しかったようだけれど、持ち前の頑張り精神で奨学生での大学進学を目指していた。グループワークではトピックの中心にいることは少なかったが、必ず存在感を放っており、議論が脱線しそうな時はすぐに本題に戻すような力を持っていた」
などなど。
ニッキーはそんな書き込みを読みながらため息をついて、年季の入ったiPadの画面を暗くする。
自宅のリビングのソファーでニッキーは、隣の部屋でパソコンを前に何かをしている弟たちを見た。
今日は休日であり、ラルフは家に友人のゴルゴを呼んでいた。二人は数日前からパソコン上で何やら制作をしているようであった。ニッキーはそれを覗いてもさっぱり何をやっているのか分からなかったし、恐らく聞いても分からないので会話には加わらなかった。
図書室の一件からもうすぐに一週間が経とうとしていた。
巻き込まれて怪我をした生徒もいるらしく、死者が出たことで精神的にナーバスになっている生徒もいるようだ。しかし、少なくともニッキーの目の前に居る二人の当事者たちには目に見える影響はないようだった。
やがて、ラルフたちは数冊の本を持ってリビングの方へとやって来て、コーヒーを入れるとそれらを読み始める。
ニッキーはiPadで適当にニュースサイトを巡っていたのだが、いつの間にか隣にラルフが移動してきて座っていた。
「なあ、兄貴。ちょっとさ、自信が無くて話せなかったことがあるんだけどさ。こいつと話してたら、やっぱり兄貴にも相談した方が良いかもしれないってことになってさ」
「何だ。実は二人は付き合ってたみたいな話なら別にしなくても良いぞ。俺は分かってるからな」
そんなジョークを飛ばすと、ラルフは首を振って苦笑いしながら肩を叩いてきた。
まるでそれはここから話すことは決してそんな「ジョーク」が挟まるような余地なんてないと言いたげだった。
ラルフの態度に、ニッキーは襟を正すように座り直し彼の言葉を真剣に受けようとした。
「図書室の棚が倒れた事件。もうみんな事故だということにして、原因をこじつけでも良いから作ろうとしてるやつさ」
振られた話題にどきりとした。
「あれは殺人だぜ。不運な事故なんかじゃねえよ。計画的に仕込まれた『椅子取りゲーム』ってやつなんだよ」
にこりともせずにラルフは言う。
「殺人? なら、あのエリスって子は誰かに殺されたのか」
「こっち来てみろよ。ぶったまげるようなことが分かるぜ」
そう隣のパソコンのある部屋に呼んだのはゴルゴだった。何やらマウスを操作して画面を閉じたり開いたりしていた。
ニッキーは図書室での一件を事故としか考えていなかったので、まだ弟たちは何かの冗談に自分を巻き込もうとしているとしか思えなかった。
「数日前からフェイスブックを覗いてたんだが、ちょっと気になることがあってね。きっかけはこいつの冗談だったんだけど」
ラルフはフェイスブックの自分のページを呼び出すと、そこに書き込まれた無数のメッセージをツリー状に展開した。一つのトピックの下に何十個もの書き込みがあり、その下にさらに同じような返信がされていた。
「これは俺のクラスメイトだけが見られるやりとりさ。ちょっと呼びかけてみたら、この通りだ」
得意そうに言うと、ラルフが最初に投稿したと思われるトピックを見せてくれた。
「州立大学給費学生、繰り上がりで採用されているやついるよな」
そんなラルフの呼びかけで、目の前の膨大なツリーは出来上がっていた。この問いについて様々な反応がフェイスブックをやっているクラスメイト達から寄せられていた。中には「変な憶測をするな」とか「エリスの死を変な印象で騒ぎ立てるべきじゃない」とか、トピックそのものを批判するものも多かった。
「それは俺たちだってエリスのクラスメートだ。彼女の知り合い、友人、家族をいたずらに傷つけたくはないさ」
まるで、ラルフの言葉のタイミングはニッキーがコメントを読み終えるのを狙ったかのように正確だった。
「でもよ、兄貴。もしもこの件が誰かの手によって引き起こされたものだったら、そいつを暴かなきゃならねえとは思わねえか」
ラルフの目は座っていた。
トピックによって主張されているのは、「州立大学の給費学生」の件であった。
ニッキーたちが通う高校には二年生の段階で、州立大学への推薦がもらえるようになっていた。それも、卒業までの学費を州政府が負担してくれるというもので、家庭の事情から大学進学を諦めざるを得ない者にとっては願ってもいないチャンスになっている。
サクセスストーリーが眠っていそうだとニッキーは予感した。貧しいながらも勤勉に励み、大学へ進学して給料の良い会社に入る。まさに大逆転の人生だ。
そんな風に給費学生のモデルケースを思い浮かべていた。つい、他人をドラマに仕立ててしまうのが彼の癖だった。そのせいで被害妄想が激しかったり、安易に人を疑ったり、デメリットも多いが、誰かに対する共感は人一倍に持つことができた。
ともあれ、給費学生だが、学校から選ばれるのは成績優秀者の上位五名だった。その中にエリスも入っていたと言うのだろうか。
「エリスは五番目の成績で給費学生になれていた。ギリギリだな。本人もそれを意識してたんだろう。根を詰めてたようだぜ」
トピックに連なる意見の一つに、エリスが給費学生を意識していたこと、自分が五番目の生徒だと理解していたことが書かれている。ニッキーはそれを読んで少し考えてみた。
「さっきの『繰り上がりで採用されたやつがいる』ってのは、エリスが亡くなったことで新たに選ばれたやつがいるってことか」
ニッキーがぼそぼそと言うと、嬉しそうにラルフが答える。
「話が早くて助かるぜ、兄貴。そうなんだ。今日になって本人に通知があったらしいぜ。繰り上がりで給費学生になるぞって話がされたやつが」
「……なあ、まさかとは思うが、その繰り上がりで採用されたやつが、この事件を起こした。そう言いたいのか」
数多く並ぶ書き込みの画面を見ながら、ニッキーは言う。
すると、ラルフは隣に立っていたゴルゴと顔を見合わせて、おどけたように両手を広げて見せた。
「そう考えるのが自然じゃないか? こうして大勢の人間が賛同してるんだ」
「だとしても、決めつけるのは危険じゃないか。大衆は時にあてにならない。千人が賛成していても、一人の反対意見がまともだったこともある」
「それも兄貴、映画の話じゃないのか」
「そうかもしれないし、違うかもしれない。それに証拠もないじゃないか」
ニッキーが「証拠」という単語を用いると、嬉しそうに反応したのはゴルゴだ。
「証拠はないけどよ、それに繋がる証言はあるんだ。なあニッキー、俺たちはあの現場に居たんだぜ。ちっとは信用してくれよぅ。なあ?」
人差し指を何度か振ったゴルゴは、持ち前の人懐っこい笑顔を見せるのだった。
ゴルゴはニッキーとラルフの幼なじみだった。本人はいつも首から怪しげなチェーンのアクセサリーを下げて、腕輪やら足輪をつけて喜んでいるようなやつだが、家はニッキーから見ても恐ろしく厳格な家だった。
いわゆる食事の前と就寝の前には祈りを欠かさず、日曜の礼拝には家族で参加し、一時期は各家庭に聖書を配布して教会への寄付を呼びかけるような活動もしていたらしい。
そんな家庭で育った反動なのか、ゴルゴはやたらと神とか奇跡とか運命とか、そんな言葉に反抗的な人間になっていた。
時々、ニッキーはラルフとゴルゴと一緒にテレビでバスケットボールの試合を観ることがあった。
応援するのは地元ニューヨーク、ブルックリンを本拠地とするニックスだ。あの伝統的な白のユニフォームをまとって躍動する選手達を見ながら、三人で一喜一憂していた。
そんな時でも、例えば神に祈りたくなる場面、ニックスがフリースローを与えて逆転の危機を迎えているような瞬間でも、ゴルゴは祈らない。
彼は口癖のように言うのだった。
「こんな時にばかりに頼られても、『ニイちゃん』は困っちゃうぜ」
『ニイちゃん』というのはすなわち「兄ちゃん」であり、それはすなわちイエス・キリストのことであるのだが、ゴルゴは親しみを込めてそう呼ぶのだ。
ゴルゴは自分が図書室での事故から無傷で生還したのはただ単に運が良かったと考えていて、決して彼の中の『ニイちゃん』が助けてくれたわけではないと思っている。
そして、この事件を起こしたのも『ニイちゃん』の気まぐれなどではない。ゴルゴなら必ずそう言うだろう。
「窓際の一番奥にいたぜ。この時間は必ずここで画面とにらめっこだよ、やっこさん」
ニッキーはゴルゴのささやきを聞いてから、目線を部屋の奥へと持って行った。
図書室の事故がただの事故ではなく、故意に引き起こされた「事件」である。そんな大胆な意見を聞いた翌日だった。放課後に三人は集まると、校内のパソコンルームに来ていた。
この部屋には放課後、パソコンを使うクラブ活動の生徒がいる。それでも部員数はそれほど多くないと言うか、片手で数えられるほどなので、多くの席は空きとなっているのだ。
その場所は自由解放になっているので、誰が使っても咎められることはなかった。
ニッキーは奥に座っている生徒を観察した。
黒縁のメガネは生真面目な学生を思わせるのだが、髪の毛は金髪を逆立てていた。その点はラルフと同じだったが、メガネの男の場合はその度合いが少し違った。まるで何本も棒が突き刺さっているように尖らせていたのだった。口をへの字に曲げて眉間にはカルフォルニアバレーのような深い堀がある。
第一印象が「気難しそうな男」だった。
ニッキーは彼を見ながら、昨日、ゴルゴに言われたことを思い出していた。「証拠はないけれど、証言はある」。どういうことだろうかと、様々なドラマを夜通し頭の中で繰り広げているうちに、昨晩は寝てしまっていた。
それを通してニッキーが導き出した結論は、「ゴルゴがこの図書室の事件の犯人について、目星をつけている」というものだった。
「行こうぜ、兄貴。ゴルゴ。俺から話してみるぜ」
ラルフは迷いなく奥へと進むとパソコンの前に座ってる男に近づく。
「ようやく話しかけてきたか。何なんだよ君らは。数日前から入り口でうろちょろされると、気が散るんだけどな」
深いため息と不平に迎え討たれ、ラルフは舌打ちをする。
「何を考えてるのか分からないが、時間がもったいないとは思わないのかね。これを見たまえ」
男は左腕を捲って腕時計を見せてきた。デジタル式のその時計は時刻ではなく、ストップウォッチになっており、現在は停止しているようだった。
時間は一時間と二十三分を示していた。
ボタンを操作してそれをゼロへと戻すと、時計を隠すのだった。ニッキーは彼の腕の右にも時計が巻いてあるのに気がついた。
「君らが僕を監視してた時間だ。一時間三十分あれば映画が観られるぞ。どうだ、後悔してきただろう」
すかさず映画好きのニッキーが口を挟む。
「映画は大抵二時間だから少し足らないな。一時間半のもあるけれど限られてる。昔のになるほど短くはなるけどね」
「それは失礼。そういうことを調べる時間にも使えた訳だ」
「ふん、お前のような殺人犯にお説教はされたくないぜ、ギルバード」
会話が映画の所要時間という話題に入って、弛んできた時だった。
ラルフはギルバードと呼んだ時計の男を、何のためらいもなく、いきなり、稲妻のように「殺人犯」呼ばわりしたのである。
「お、おい。やめとけよ、そんないきなり」
ニッキーは怖気づいて、つい二人の間の仲裁に入ってしまっていた。
確かにゴルゴとは「例の図書室の件で怪しい奴がいる」という話をしていたが、あくまでそれは「噂」の域を出ない程度のことだったはずだ。それをいきなり相手を「殺人犯」と決めつけるのは早計であるし、非常識極まりない。
ただ、ニッキーは弟の性格ならばこうなるのも僅かながらは納得できた。
弟のラルフは小さい頃から危なっかしくて見ていられなかった。誰かが見張っていないとすぐに危険な行為に出る。
二人がまだ幼い時、父親の近所付き合いの道具として、草野球のチームに入れられていたことがあった。
そこでラルフは投手を務めたことがあったのだが、相手のチームの一番の強打者にデッドボールを当てたことがある。相手は負傷してベンチに下がり、試合はチームが勝利したのだが、後にラルフは半ばわざと出した死球だったとニッキーにだけ自白したのだった。
もちろんわざとだと分かれば、草野球のチームから追放される可能性だってあった。小規模とはいえ、グラウンドの周りの家の人たちや、家族も応援にくる。それなりにちゃんとしたチームなのだ。
しかし、ラルフは誰にも悪びれずにニッキーに本心を告げた。「相手は避けようと思えば避けられたよ。それに四球出すより球数も節約できたしね」。
そんな突拍子もないことを言い出したり、実行し始める弟をニッキーはいつでも心穏やかに見ていられなかった。
それでも見捨てる訳でもなく、いつでも側にいて何かあれば味方になってやりたいと思っていた。
だが、積極的に彼の無茶に付き合うような度胸はない。
だからこの時、弟が誰かを「殺人犯」と言い放っても、追従して賛成するようなことは出来ず、はらはらしながらその行方を見守るので精一杯だったのである。
パソコンに向き合っていたメガネの男、ギルバードと呼ばれた彼は、渋い表情を一つとして変えずに左腕の袖を捲る。そして、ストップウォッチを操作するのだった。
カウントアップが唐突に始まった。
「君らのことはよく知っている。ラルフにゴルゴ。学業成績は真ん中あたり、そして常につるんで学外で散々悪行を働いているそうじゃないか」
ギルバードはまるで教師のような立ち居振る舞いで述べた。
「人を殺すまでのことはしてないぜ。自分が死にそうなことは何度かあったけどな」
それは弟なりの皮肉だろうが、全く目は笑っていない。ギルバードも同じく仮面を被っているのではと思われるほどに表情を変えなかった。
「ギルバード。お前がエリスを殺した。でたらめなんかじゃないぜ。根拠もその動機も揃ってるんだ」
またしても率直に言い放っていた。言葉の一つ一つにニッキーは怯えるようだった。自分に向けられている訳ではないが、その向こう見ずな弟の言葉は危なっかしくて、事態を静観できない。
「まず、お前はエリスの次に大学の給費学生に選ばれていた。それを教師から告げられていた。その証拠もあるんだぜ」
ラルフはポケットからスマートフォンを取り出すと、画面をここにいる人物たちに見せるのだった。
「給費学生の成績リスト……?」
それはパソコンの画面をカメラ機能で撮影したものであった。表計算ソフトで作成されたシートに生徒の名前が書き連ねてあり、そこに成績と順位が表示されている。
名簿には六人の名前が見える。恐らくこの画像の下の方にも生徒の名前は出ているだろうが、上手く外して撮影されているのか、それとも編集されているのか、とにかく六人しか名前は確認出来ない。きっとこの一週間、ラルフたちはこういう証拠をパソコン上で集めたり、犯人に突きつけるために編集したりしていたのだろうな。
この中の上位五人が給費学生として州の支援を受けて大学に通えるらしい。
ニッキーが目を細めると、五人目には確かにエリスの名前があった。
そして、そのすぐ下、六人目に記されている名は「ギルバード・ハーバー」。腕時計を二つ巻いている目の前の彼だった。
確かにこれを見ると、五人目のエリスがいなくなれば六人目のギルバードが繰り上げで給費を受けられる。
「給費学生の締め切りは一ヶ月後だ。そして、先月、ほとんど最後の評価の機会となるテスト期間が終わった。ギルバード、お前はテストの点数が悪かった。だから、このままじゃエリスに勝てないことを考えて、殺したんだ」
断定口調をラルフは崩さない。
流石にその話の流れはおかしいとニッキーでも思った。
もちろんギルバードは反論してくる。
「エリスじゃないても良いのでは。上位五人の誰か、誰か一人でも消せば繰り上げになるが」
「ギルバード、お前はエリス以外の選出者を言えるか?」
そこでギルバードは初めて顔をしかめる。
すかさずゴルゴが会話に入ってきた。
「知らないだろうなぁ。お前はテストが終わって担任に呼び出された。その時に話があったはずだろ。『お前の成績じゃ給費生は無理だ。惜しかった、惜しかったぞギルバート。あとはニイちゃんにお祈りするかー、黙って就職するかー、とにかく考えてくれよな』って感じによ。んで、自分が滑り込めずにギリギリでアウトになったことを知る。でも、知ったのはそこまでだよなぁ? 選出者については知らされなかったはずだぜ」
「そうだ。俺たちは他の選出者に聞き込みもした。証拠のムービーもある。選出者たちは、他の選出者の情報を全く知らなかった。けれどな、ギルバード。お前は給費生を諦められなかった。だから、こいつに話を聞いたんだ」
ラルフは言い終えてから一つのムービーを再生し始めた。画面にはなで肩でメガネの男が映っている。
彼は食堂かどこかでラルフたちとインタビューじみた会話をしており、その中で聞き逃してはならない言葉が出てきた。
『そうだな、やたらギルバードはパーティでの会話にこだわってたな。多くの人にさりげなく聞いてたみたいだぞ。給費学生のことも、その時に聞いたんだろうぜ。俺がサプライズで用意したケーキのことも話したぜ。おっ、お前も聞くか? 家の事情でブルックリンから離れなくてはならなくなったエリスが、いかにこの街を愛して、両親に争い、そして猛勉強の末に給費学生になったかを……』
嬉々として話す、浅黒い肌の男が映像には映っていた。彼が何者かは分からないが、ニッキーは何となく違和感があった。その正体を確かめられないまま、続くラルフの主張を聞くことになった。
「こいつはエリスの知り合いで、三年生のゲイリーってやつだ。ゲイリーから聞いたらしいじゃないか。そう聞いたぜ。なあ、どうなんだよ」
「そんなお調子者は知らん。ゲイリーなんて名前も聞いたことはないな」
ここで初めてギルバードがラルフの言うことを否定した。
「おーっと、その言い逃れは出来ねえぜ。写真もあるんだ。ほれ」
すると、すぐさま差し向けるが如く、ゴルゴがスマートフォンを滑らせてきた。
表示されているのは、一枚の写真である。
そこにはパーティ会場らしきところで、先ほどの浅黒い男、ゲイリーと話すギルバードの姿があった。どうやらエリスがケーキを食している場面を写したものらしいのだが、その背景にしっかりと横向きのギルバードと、同じくゲイリーが写り込んでいた。二人はジュース入りのグラスを手に何かを話し込んでいるようだった。
「これは……」
ギルバードは驚いたように声を上げる。
「これだけじゃ、何を話してるのか分からないだろう」
「お前はこのゲイリーを知らないって話したろ。それは嘘だったわけだな。このパーティーで話してたんだからな」
ラルフが指摘するとギルバードは目を細めて今一度、その写真をあらためていた。
「こいつの名前はゲイリーなのか?」
「とぼけようとしても無理だぜ。証拠は上がってるんだ。ははは、観念しろよ。何ならこいつに話を聞いてみるかよ。それとも、ここに呼んでみるかー?」
「いや、それは時間の無駄になるだろう。そいつは俺を知ってると言い、俺はそいつを知らないと言わせてもらう」
「それならこの写真は何なんだ。合成だとでも言うのかよ」
ラルフが問い詰めると、ギルバードは暫し考えるような表情をしていた。
先ほどからすっかり場から追い出されるようにして、話の中心から弾き出されたニッキーだった。今は三人のやり取りを息を飲んで見守っていた。
ニッキーの周囲の人間は皆、あの図書室での件は事故だと結論していた。
だが、その一方である疑問も共通して抱いていたのだ。
本棚が次々に倒れたということが起きるとしたら、どんな「事故」なのだろうか。
地震がその日に起きたという報告は、どこからもされていないはずだった。何かのバランスを崩して本棚が倒れる。それは決して「自然に起こった」ことではないような気がしていたのだ。
だとしたら、やはりこの事故は人為的なものが働いた「事件」なのだろうか。
「さっきのビデオの人物と、この写真の人物は別人じゃないのか。今から確認しに行くのは、時間の無駄にはならないだろう。どうだ?」
ギルバードはニッキーが抱き始めた疑いを振り払うかのように、冷静に告げるのだった。
「それで納得してくれるんならいいけどよう、後になって言い訳しないでくれよな」
ゴルゴが答えて四人はパソコン室を後にする。
彼らの通う高校はブルックリン区の図書館の側にあり、景観が昔ながらのヨーロッパ風のアメリカ建築であったために、観光客達がこぞって写真を撮りに来る。学校の門の側でカメラを操作する人々を、廊下の窓から見る。ニッキーはその人達がどの国からやって来たのかを考えていた。アジア人風だったので中国か日本だろうか。
移動してたどり着いたのは三年生の教室だった。ニッキーの隣のクラスであり、そこにはまだ多くの生徒が残っていた。
ニッキーは昨日、学校のクラスメートたちで作るフェイスブックのページを見ていたので、この場で来週に行われるハロウィンについての話し合いがあるのを知っていた。エリスの件があって自粛する空気もあったのだが、「暗くなって萎んでいるばかりじゃ、この先何年経ってもハロウィンの季節が来る度に鬱々してしまう。ここは目一杯楽しもう」という誰かの書き込みによって空気は一変して、こうしてハロウィンに向けて何か催し物を始めようと話し合いが行われているのだった。
ゴルゴが先頭になって入って行くと近くの女子生徒に事情を話して、ゲイリーの所に案内してくれた。
確かに、少なくとも、ニッキーたちが直面したのは、ビデオに出演していた男子生徒そのものだった。ゴルゴは彼と握手をしてからニッキーたちを一瞥して「何事だ」という顔をしていた。
そこでスマホのムービーを音を消したままで見せて、「この前のインタビューだぜ。これに出てる本人が本当にゲイリーかって、変なことを聞くやつがいてよ。んで、会わせてやろうって話になったんだよ」とゴルゴが伝えるのだった。
すると、ゲイリーは首が取れてしまうのではないかと思われるくらいに頷いた。
「これは確かに俺だぜ。男前に撮れてるだろう? ははは。また何でも聞きたいことがあったら来いよな」
そんな風にゲイリーは告げてくるのだった。まるでブルースでも歌っているかのように、どこかもの悲しいしゃがれ声であった。
またしても違和感が走る。
ニッキーはゲイリーの態度と、そしてスマホの動画のゲイリーの姿に何か不自然なものを感じていた。
写真の方も確認は取れて、これでギルバードがエリスを殺害する動機は揃ったことになった。
「これで決まりだな。エリスを殺したのはあんただ。これから誰かに話して警察に突き出してやる」
四人で教室から出て扉を完全に閉じてから、ラルフが宣言する。
「おいおい……ちょっと待ってくれ。早急すぎるぞ。確かに動機はあるかもしれないけれど、まだ証拠がないだろ。どうやって図書室で殺人を行ったって言うんだ。それが分からないうちはまだ」
「兄貴は弱虫だ。こいつが悪いことは全て分かったんだ。犯罪の方法? 証拠? そんなものは警察で話してもらえば良いじゃないか。自白させるんだよ」
突然、ラルフに牙を向けられてニッキーは何度か瞬きをした。滅多に弟と喧嘩をしない彼だったが、時折、一年に一度くらい、本気で弟を怒らせてしまうことがある。その時のような反応をラルフは見せているのである。
しかしながら、いつもの怒りとはどこか違っている。感情に全てを委ねるような態度ではない。発露しているのは怒りの気持ちだけではない。何かが混ざっているのだ。ニッキーはラルフの言葉を真っ直ぐ受け止めたのだが、その正体は掴めなかった。
ニッキーとラルフがにらみ合っていると、割って入ってくる声があった。
その人物は左腕のストップウォッチを停止させてすぐさまゼロに戻す。
「今まで数えてきた時間をすっかり無駄にすると思ったが、事情は変わった。どうやらこの件は本当に事件のようだな」
ギルバードがニッキーたちを見回してから冷静な口調で言うのだった。
どうして自分が犯人だと目されており、なおかつ追い詰められる立場であるはずなのに、ここまで落ち着いていられるのだろうかとニッキーは疑問に思う。
「認めるのか、認めないのか。それだけ聞かせてくれ。あとは、それこそ本当に『時間の無駄』だからな」
「まだだ。俺がもしも万が一、何があってもそれはないのだが、犯行を認めるのだとしたら、この謎が解かれた時だ。『どうやってエリスは殺害されたのか。そして、その証拠はどこにあるのか』。この疑問が解消されない限り、誰が犯人であったとしても、そして例え事故であったとしても、誰の納得も得られないぞ」
思わずニッキーは頷いてしまっていて、ラルフから睨まれることになってしまう。
確か家では「ギルバードが犯行に及んだ証拠はない」とラルフは断言していなかったか。ニッキーは思い出していた。それならば、犯罪は立証できないままになってしまう。
だとすれば、ギルバードは無実でなければならない。
きっと百の怪しいと思える状況証拠を積み重ねてみても、物的な証拠が出てこなければ、もしくはギルバードに優位な物的な証拠が出てくれば、その場で彼の無実が確定する。必要なのは確実な物的証拠のみなのだ。
証拠という言葉に、まるで眠ってしまったかのようにラルフは沈黙してしまっていた。
頼りとなるのはゴルゴだけだったので、彼の言葉を待つと、いつものようなふざけ半分といったような声が返ってくる。
「もちろんその辺も抜かりないぜ。ただなあ、今は図書室には出入りが制限されているだろう? どうしたもんかなあ。図書室に入れてもらえれば、全部つまびらかになるんだかなあー」
「その、わざとらしい誘い文句、気色が悪いぞ。言いたいことは分かった。要するに、図書室に忍び込めればいいんだろう」
「話が早くて助かるぜー。そうだなあ、夜なんてどうだ? 明日は休みだぜ。それとも、エリスから奪った席を守るのに勉強で忙しいかなあ?」
「変に挑発しなくてもいい。こちらは逃げ隠れしないぞ。時間を合わせるか」
ギルバードは律儀にもメモを懐から取り出して、ゴルゴと待ち合わせの時間を書き留めているようだった。
夜に図書室に忍び込むつもりらしい。
そんな映画みたいな非日常への誘い、ニッキーの胸が踊らない訳はなかった。事態が事態で不謹慎であるとは自覚していたが、自らの興味は奪えない。
「図書室は封鎖されてる訳じゃないんだよ、兄貴。ちょっと鍵がかかってるだけなんだ。だから、ぶっ壊して今すぐにでも入れば良かったんだ」
縦長の缶に入ったカフェインを多く含む清涼飲料をあおりながら、ラルフは繰り返し文句を述べていた。
「そういうこと、あまり外で言うなよ。疑われるだけじゃ済まねえぞ」
その隣で缶コーヒーを飲み終えたニッキーが独り言のように言った。
ゴルゴとは夜に会う約束をして別れ、ニッキーとラルフは帰宅の途についたのだが、その最中もラルフはタイマーの切れない目覚まし時計のように話し続けるので、たまらずニッキーは近くの公園へと彼を誘導し、そこで思う存分に毒を吐かせることにしたのだった。一度彼の主張が終わって、怒りは収まったかと思うと、再び噴出してくる。その繰り返しだった。
「ギルバードを自由にしたことの方が重大な問題だ。あいつは殺人犯だぞ。野放しにしとけば、証拠を隠すかもしれねえ。なあ、兄貴。そうなりゃもう事件は迷宮入りなんだぞ。後になってこの選択が全ての間違いだって気づいても、何もかも遅いんだぞ」
「でも、ギルバードは約束した。今日の夜、図書室に来るんだから、それで良いじゃないか」
これもまた何度となく告げた言葉だった。
二人の後ろを自転車が通り過ぎた。
この公園は港に接しており、観光客も数多く見られるような景観の美しい場所だった。ニッキーとラルフは港に接する丘の、仕切りとなるフェンスに寄りかかって話している。
落ちかけている陽が水面に光をいっぱいに広げて、建物の影となっている場所まで手を伸ばしていた。
遠くからストリートバスケをする少年たちの声が聞こえてくる。五、六人のうち二人くらいはニューヨークニックスのTシャツをデザイン違いで着ている。それを見ると、ニッキーは呟いた。
「今日はバスケ観られそうにねえな。あの四番のセンター、名前なんて言ったかな。怪我から今日帰ってくるらしいぜ」
ラルフはその言葉を聞くと、目元の辺りを押さえて、何か言いかけた口を一度閉じると、そこでようやく不平を吐き出すのを止めるのだった。
ボールがリングに跳ね返される音がやけに大きく聞こえて、今度はニッキーから話を切り出した。
「お前はこの事故だか事件だかに巻き込まれたから、俺なんかとは意識が違うんだろうけどさ。それにしたって、ここまで首を突っ込む必要があるのか?」
「兄貴は気にならねえのかよ。ギルバードを許すのかよ」
「そういう訳じゃねえんだ。どうして俺らがこんなことをしなきゃいけないんだってことだ。何だったら警察にこれまでの話をすれば、本当のことが分かるかもしれねえ」
ラルフは俯き加減になって押し黙ってしまう。
彼も警察を信じていない訳ではないのだとニッキーは思っていた。
第一、この出来事には不可解なことがある。
本棚の下敷きになって亡くなった少女がいて、その棚が倒れた原因がまだどこからも発表されていないのだ。
事故なら事故で、目撃証言なり自供なり、どこからか話が漏れてくるのが普通だろう。騒いでいて本棚を倒してしまったとか、棚が脆くなっていて崩れてしまったとか、そういう説明が出てくるべきなのだ。
しかし、未だに真相は明らかになるどころか、見解さえ確かなものが出てきていないというのが現実だ。
ニッキーは警察もきっとこの事故に何か引っかかりを感じて捜査をしているに違いないと考えていた。
だからこそ、警察の発表を待ちたい。待つべきだというのがニッキーの意見だ。ここで自分たちが積極的に首を突っ込んでいく必要はない。
ラルフもそれくらいは分かっているだろう。
そう思うからこそ、ニッキーは弟の切羽詰まったような行動の数々に疑問を抱くのだった。
あくまで捜査は警察に任せるべきだ。病気は医者に、機械の故障は機械のメーカーに頼むのが効率的だ。そう言わんがばかりに告げた言葉に、ラルフは唇を噛んで何も言わなかった。
もどかしげに清涼飲料を流し込むと、「バスケはネットでハイライトを観ればいいさ。とにかく夜だよ、兄貴。ギルバードが来なければそれだけであいつの弱点が増えるから、俺たちは行かなきゃ。あと、四番のセンター、名前はサンダースだ。俺はあまり期待してないけど、今日の試合は活躍する気がするね」と早口で告げて地下鉄の駅へと向かっていくのだった。
深夜に外出するために僕らは寝室の窓から長めの脚立を使って抜け出す。そして、自転車でいつもの登校の道のりより倍の時間をかけて、夜の校舎へとたどり着いた。
すでにゴルゴとギルバードは閉ざされた校門へと集合している。面々が揃ったのでいざ図書室へ、となったのだが、当然のことながら門は閉まっている。無理に乗り越えようとすれば、何らかの警報装置が作動して痛い目をみるだろう。
ニッキーはどうしたものかと考えていたが、その点についてはゴルゴが全ての解決策を持っているようだった。
「こういうのは『ニイちゃん』の裏をかくんだよ」
そう述べたゴルゴは校舎に面している廃ビルへと一行を案内し、二階の割れた窓を開けた。すると、ちょうど校舎を囲む鉄柵の頂点が見える。
「乗り越えるだけが壁じゃねえのさ。なあ、『汝、道が開かれぬ時は道を疑うべし』」
ゴルゴのその言葉は聖書の引用かもしれないし、そうでないかもしれない。どうあれゴルゴは近くにあったトタンを何枚も柵の上に重ねると、即席の橋のようなものを作って夜の校舎への道を作るのだった。
誰一人何も話さなかった。足音が響き、件の図書室が見えてくる。扉には鍵がかかっていたが、ゴルゴが懐から鍵を取り出して解錠した。
「お前らと別れた後にちょっとな。全くよう、今日で一学期分の勉強をした気分だ。教師の一人に『前回のテストで分からないところがある』って話したら、喜んで夕暮れまで教えてくれたぜ。何でも俺は『やればできる生徒』なんだそうだぜ」
ゴルゴははしゃぐように言うとするりと鍵を回して、皆を室内に案内するのだった。
つまり、ゴルゴは鍵を手に入れるためにわざと職員室に行って勉強を教わるふりをし、そのまま自由に動ける機会を窺っていたということだ。これには少し教師が可哀想に感じた。確かにゴルゴはニッキーからすれば十分に勉強ができるし、本腰を入れて取り組めば給費学生になることも非現実的な話ではない。そんな生徒がやる気を見せてくれたとしたら、教師とすれば張り合いを感じることだろう。
そんなことをニッキーは考えつつも、無音の図書館に足を踏み入れた。
すると、何かの電子音が聞こえた。ニッキーの隣でギルバードがストップウォッチを操作している音であった。
「時間のことなんて気にしていられるのかよ」
「それなら俺は十五分したら一人でここからお暇させてもらおうか」
ギルバードが述べるところによると、今日もおそらく当直の教師はおり、夜間の見回りも予定されているだろうということだった。
見回りの頻度だが、流石に一時間に一回ということはないだろうし、一晩に一回というのもないだろう。だが、その見回りの教師に発見される確率は、結局のところ滞在した時間が長ければ長いほど高くなる。
そんな当たり前の理屈から、ギルバードは十五分という制限時間を設けたらしい。
彼のそんな講釈を聞くと、ニッキーだけでなくラルフやゴルゴも納得して従うことに決めたようだった。
「それでは手短に、かいつまんで、お願いしようか。この本棚の謎を」
ギルバードが、倒れたままになっている本棚の横に立って言った。
「十五分かー、十五分ならジョークを混ぜてる暇もねえなあ。仕方ねえ、んじゃ僭越ながら推理を披露させていただこうかね」
軽やかな口調と共にゴルゴは本棚の近くに移動すると、皆を手招きで集めるのだった。
「こんな感じでよ、本棚はドミノ倒しよ。一番後ろのを起点にして、ドカドカドカって倒れてって、ガシャン」
本棚の倒れていった先をゴルゴは指差した。そこには廊下の窓ガラスを突き破って上半分が外に出ている棚があった。
「その倒れた本棚の真ん中あたりにエリスがいたんだなぁ。不幸かも知れねえが、それだけで片付けられない奇妙なことがあるんだわ」
ゴルゴは不敵に笑って本棚に近づいて、その一番後ろの棚の側でしゃがみこんだ。
辺りにはまだ本が散乱しており、事故当時の状況をなるべく保持しようとしているようだった。
倒れた本棚の中で残っているのは、一番後ろの一つと、その次と次の二つ。そこからはおおよそ三つほどの本棚のスペースが空いているが、おそらくここにエリスが挟まれた本棚があったのだろう。そこからさらに二つの本棚がしなだれかかるように倒れており、最後の一つが窓を突き破っていた。
落ちている本を踏まないようにしながらニッキーはゴルゴの側へ行く。ここで一人、人が亡くなっていると考えれば、不気味になってくる。
その思いはラルフやギルバードも同じようで、ためらう様子を見せつつも、ニッキーに続いた。
「この本棚はよう、確かに背も高いし巨大で、押し潰されたらひとたまりもねえ。でもよ、みんな疑問に思うんじゃねえか? この、最初の本棚。これを倒すのにどれだけの力が要るのかってな」
ニッキーの説明を聞きながら本棚を観察する。
彼の言う通り、棚はニッキーの背よりも高く、木製で厚みもあった。押し潰されればひとたまりもないだろう。
そして、誰もが何度も抱いていたであろう疑問。
これをどうやって倒したのか。
「聞くところによれば、本棚にもろに挟まれたのはエリスだけということになる。他に怪我人がいないんでな。そこから、分かるのはよ、倒れた瞬間を知るのはあいつだけってことなんだ」
「残り十三分だ」
ギルバードの冷静な言葉が場に投げかけられる。それはまるで、一気にゴルゴの説明通りに話が進んで、その勢いで推理の粗が見逃されることに警告を発したかのようだった。
「こう思わねえか? 倒すのはエリスを挟んだ一つだけでいい。エリスが本棚に入った瞬間に、それだけを倒せば全てがうまくいくんだ」
「なら、倒れた残りの本棚はカムフラージュか」
素早いニッキーの断定にゴルゴは頷いていた。
「それならエリスを挟んだその一つの本棚を倒して、それから他の本棚も倒してって、そんなことしてたら見つかっちまうぜ」
ニッキーの疑問に答えるのはまたしてもゴルゴだ。
「そうだな、ニッキー。ははは、それにな、これまた変な話だが、本棚を倒したやつを誰も目撃してないらしいんだ。エリスを潰したやつはおろか、これ全部、勝手に倒れたってみんな言い放ってんだぜ」
両手を広げて大げさに説明するゴルゴの様子は、まるで舞台役者だった。
「となると、誰かが押したわけじゃねえ、それなのに本棚は倒れた。これは『ニイちゃん』の仕業じゃねえのか? なあ。だから、この事件はこれまで捜査が止まってきたんだと思うぜ。目撃者が誰もいねえ」
ニッキーが何度も頭の中で思い描いた疑問が、今ここに再現されようとしていた。
本棚の倒壊。それが本当に偶発的に起こったと言うのだろうか。
クラスメートたちは皆、警察との面談をしたという。ニッキーもその場にいた近くの人間だったからいくつか質問をされた。事件発生時にはどこにいたのだとか、怪我の具合について聞かれたが、ニッキーはほぼ正確に自分の行動を話して、捜査員から「びっくりするぽど君は無関係だな。無関係オブ無関係だ」とよく分からない評価をされていた。
それはともかくとして、ニッキーはともかくとしてラルフのクラスメートたちから何の情報も得られていないというのは信じ難かった。
ニッキーはつい脅迫を疑ってしまうところだった。クラスメートたちは何らかの秘密を共有しており、誰もが共犯である。クラス全体が犯人という展開は何かの映画で観たことがあった。
「クラス全体が示し合わせて目撃者を隠してるっていうのは、どうかな」
ニッキーが言うと、ゴルゴは嘲笑うわけではないが楽しげな笑みを浮かべて返すのだった。
「その映画のような話。さすがはニッキーだぜ。脚本家にでもなるといい。でもよう、俺とラルフもクラスメートだ。そういう『示し合わせ』みたいな話は聞いたこともねえし、もしも、エリスが皆から嫌われていたら、あんな給費生のお祝いパーティをしたり、こうして俺らの捜査に協力したりするだろうかな」
ニッキーはゴルゴに見せられたパーティの写真を思い出していた。あの時の、誰もが心から喜んでいる笑顔が作り物だとは思いにくい。
「時間もねえだろうし、続けようぜ」
「残り九分だ。そろそろ足音が聞こえ始めてもおかしくないな」
「脅かすなって、ギルバード。そうだな。ここからの推理はラルフに任せるとするかな。時間を気にしながら話し続けるってのは、どうにも苦手でよう」
ゴルゴはおどけたように言うと、仏頂面で立っているラルフの方を見やる。
「推理はこうだ。犯人は後ろから本棚を倒したんじゃない。前から本棚を引き倒したんだ」
腕組みをしたままでラルフは言った。まるで、ここで話が振られることを分かっていたような落ち着きようである。
「前から引いた? でもよ、前からだったら、犯人も挟まれるぜ」
「ああ、違うのさニッキー。前からってのは、本棚の前からってことじゃないんだ。いや……いいのかなあ」
ゴルゴがすかさず反応するけれども、ラルフが片手の平を見せて「俺が話すから」と説明を引き受ける。
「いいか、兄貴。前からって言うのはよ、本棚を前からって意味でもあるけれど、ドミノ倒しを前から行ったってことなんだ」
ドミノ倒しを前から。
その言葉から連想した光景は、一番前の本棚を倒すことが後ろの本棚の倒れる原因となる……というものであった。
いや……それでは「ドミノ倒し」が成り立たない。どうやったら前から倒れていく棚が後ろの棚を押し倒すような原因となるのだろうか。
そんな風にニッキーが考え込んでいると、ゴルゴとラルフは倒壊した本棚の先頭、ガラスを突き破っているものの側へと歩いて行く。時間ももうないという意識はどこかへ行っていて、今は彼らの推理を理解したいという思いが強い。
ちょうど映画のクライマックスで時間を忘れてしまって画面に食い入る時の感覚に似ている。
「ガラスが割れたというのがなあ、このトリックの肝になってるんだぜ。いいか。棚の上の方にはどれも本が入っていねえんだ。例えば、この棚は作者の頭文字がEからIまでのものになってるよな」
先頭の本棚にはインデックスとなるプラスチック製の細い板が取り付けられていて、そこには「E~I」という文字が見える。
「ここらに散らばってる本、どうだ? Eの作者の本なんてねえだろう?」
調べてみると確かにそうだった。本棚は傾いていたが、壁にめり込むようにして先頭のものは中途半端な角度になっていたので、まだ本が残っている。しかし、どれもがFないしはGの作者、そしてわずかにIの文字が名前に入っている著者たちの本ばかりだ。
「で、来てみろや。どこだったか、ラルフ? 本を隠すなら本の中っていうけどなあ」
ゴルゴは一行を手招きし、肝心の場所をラルフに尋ねていた。すると、迷う様子なく彼は動き出して案内するのだった。
図書室のカウンターの側にあった、二段構造のカートに本が積まれている。本来、この四輪の使い古された感じのある台車は返却された本を一時的に保管しておき、それから時間を見つけて担当の者が本棚まで移動させるためのものだろう。
それが一杯になっているというのが、既に違和感を覚えさせる光景であった。
まるで何かの「置き場」となっているかのようであった。
ニッキーにも大方の話の筋は見えたのでカートの中身をあらためてみると、そこにはEから始まる著者の本が見つかった。さらに同じように特定のアルファベッドの作者の本が固まって納められているようだった。
調べてみると、このカートに存在している本達はどれも倒れた本棚の上の方にしまわれていなければならなかったものである。
「犯人は本棚の上部をわざと空けた。そして棚の横の仕切りへロープを巻いたんだ。今回倒れた全てのものにだよ。授業の前に全て空にしておいたんだろうな。それから一本のロープを綺麗に通しておく。そうしたら準備完了だ」
ラルフがそう説明すると、段取りよく今度はゴルゴが話の続きを引き継いだ。
「そこでギルバード、お前は確かエリスに本を探しておくように頼んでいたよな。友人から聞いたんだぜ。授業で同じグループだったお前に、アメリカの重工業の歴史について探すように言う」
まるで歌でも歌うように上気しきったリズムでゴルゴが述べ続けていく。
それはまるで映画の終盤で主人公が名演を披露するパートのようだった。
「これだぜ。あの時の図書室での授業は、各グループに別れて調べ物をするってやつだ。俺とラルフはよう、アメリカの建国の父たちについてってやつだ。ま、一種の『ニイちゃん』だぜ。それはどうでもいいがよ、お前は直前にエリスに頼んだだろう。『J』から始まる作者の本を。これが証拠さ」
ゴルゴは楽しそうに笑いながら懐から紙を出して、スマートフォンの灯りでそれを照らした。「グループ学習のまとめ」と書かれた紙である。それが何か分からなかったのでラルフに聞いてみると、何やら思い出すような仕草をしてから、「一人に一枚配られたんだ。まとめて個人でシートを作成してそれを教師が集めて採点する」と口調があやふやなのが気になったものの、ニッキーはその説明で満足して話の先を促していた。
「それが証拠?」
「これは間違いなくエリスのプリントだ。ここに書かれているのは、参考にするべき本のリスト。それがグループ全員のプリントに書かれているのも確認したんだぜ。つまり、ギルバードがメンバーに提案して……エリスに本を取りに行かせる。そうすれば本棚の間に彼女は来るだろ? そこでタイミングを見計らって、少し開いたガラスの扉からロープを引っ張る。すると、一番奥の本棚が前に倒れてドミノ倒しになり……エリスを下敷きにできる。そこからはロープを引っ張って回収して何事も無かったかのように図書室に戻るんだ」
ゴルゴの推理を整理してみた。
きっとエリスと同じグループになったギルバードはメンバーに「この調べ学習をするなら、最適な本がある」とある一冊を紹介した。それをメンバーは書き記した。
ギルバードはそれからエリスに本を取りに行かせる。作者の頭文字は「J」だ。
しかし、「J」から始まる作者の本はそこにはなく、困惑するだろう。
時を同じくしてギルバードは外に出てロープを引いて、本棚を倒れさせる。そして、ロープを回収する……。これが全ての推理のはずだ。
「間違いねえのはよ、ギルバード、お前の持ち物からその『ロープ』が出てくることだがよう。それは警察に任せるとするぜ。さあ、どうする? 言い逃れができるならしてみろ」
両手を広げて挑発するようなゴルゴの言葉に、ギルバードは無言のまま彼を見据えていた。
本当に犯人はギルバードなのか。
ここまで犯行を指摘されて、次の一秒後には彼が自供を始めるかもしれない。そう考えるとニッキーは固唾を飲んで状況を見定めようと、すっかり二人の間に漂う空気を全身で感じ始めた。
誰も何も話さない時間が流れていった。
ふと、ニッキーはギルバードの顔つきを見て、あることに気がついていた。
彼の顔から感じられるのは「言い逃れをしようとする犯人」のものでも「無実を証明しようとする一般人」のものでもなかった。
眉間の皺を深くして思考するのはこの事件の真相のような気さえさせてくれる。
ギルバードはゴルゴの描いたのとは違う結末を導こうとしているようだったのだ。
場を収めるべき言葉を誰も持ってはいなかった。
そこでニッキーは誰かが階段を上がってくる音を聞くのだった。
当直の教師に違いない。きっと、深夜の校舎の巡回に来たのだ。ところがその足音はこの場の皆に届いているはずなのに、誰も動き出す気配がなかった。
慌ててニッキーは全員に教師の接近を知らせ、半ば無理矢理、皆を図書室から追い出すと元のように鍵をかける。
そして、ライトを照らしながら歩いてくる教師とは逆の方へと逃れていくのだった。
元来た道を通って校舎の外に出ると、ゴルゴはギルバードに告げる。
「どうだ? 自首する気になったか?」
「しないと言ったらどうするんだ。この場ですぐに俺を通報するか?」
返す言葉に全くの弱さはなかった。通報できるわけがないとギルバードは読んでいるかのようにさえ感じられるのだった。その強気な態度の理由がニッキーには分からない。
「通報してやるぜ。こいつがエリスを殺したって言ってやる。証拠だって揃ってるんだからな」
まるで喧嘩でも始めようかというようなラルフの言葉を、ギルバードは一度睨み付けるだけで返事をしなかった。
「本当にそれで良いのか。この場には迷っている者もいるだろう。その理由を突き詰めていった結果、俺を通報するのならばそれはそれでいい。だが、真実はゴルゴの語られたとおりとは限らないと思うがな」
ギルバードは思わせぶりに言う。
そして、この場で彼を通報しようということに迷いを持っているのはニッキーであった。
確かにゴルゴの示した証拠や証言は全てギルバードを犯人だと示している。
しかしながら、決定的なものがまだ不足しているように感じていた。
それだけではない。
ゴルゴやラルフが生み出した推理には「どこか穴がある」ようにも思えるのだった。
一度鑑賞した映画を頭の中で再生して大切なシーンを拾い集める、ということをニッキーはよく行っていた。
それを同じ要領で、ギルバードを疑い始めてからこの夜までの出来事を思い返して、重大な場面を再び頭の中で再生してみた。
ギルバードが州立大学への給費生に繰り上げで合格したこと。
エリスが給費生だと彼が知ったきっかけについて。
そして、実際にエリスを手にかけたこと。事故に見せかけた殺人の方法について。それらを指摘したゴルゴやラルフの推理について。
全ての謎が絡み合ってニッキーの中で一つの選択を迫ろうとしていた。
本当にギルバードが犯人なのか?
それが誤っているとしたら、一体誰がエリスを殺したのだろうか?
続く
「ニューヨーク州には隠されたもう一つの区がある」
そんな謎めいた言葉を手がかりに冒険をする二時間くらいの話だった。
ハイスクールの学生であるニッキーの頭に、その映画の思い出がよぎった。今は地理の授業中で、ニューヨーク州の成り立ちについて説明が続いていた。
しかし、ニッキーの意識はすっかりとその映画の思い出に傾いていた。
親子愛をテーマにしたハートフルなドラマで、ニッキーは二十回程泣いた。あまりにも泣きすぎたので、隣に座っていた老紳士が驚き、「そこまで手に汗握る映画だったかね?」と聞いてきたものだった。ニッキーの流した涙は顔全体を濡らし、それを老紳士は汗と勘違いしたのだろう。
(映画のタイトルは確か)
教科書に目を落として思い出そうとする。
だが、うまく皮の剥がれないチキンのように、もがいても記憶は取り出せなかった。
授業の終わりの時間を教室の時計で確かめると、残り五分ほどだった。
映画を見て過ごす五分は一瞬のようだが、退屈な授業での五分は永遠に感じる。
あと五分耐えれば今日の授業は全て終わり、自由の身になれる。
そんな風に考えていると、遠くから深く響く音がした。
二度、三度と地面が震えるような轟音。
そして、ガラスが何枚も割れる音が続いて聞こえてきた。
気づけばニッキーは教室から飛び出していた。クラスメートたちも同じだった。先生が制止する声も届かず、ニッキーたちは一緒になって音の方へと向かっていく。
途中で他のクラスの生徒たちとも合流し、大きな集団となった。
音がしたのは図書室からだったらしい。
(テロでもあったか? だとしたら、早く外に逃げなきゃいけない。いや……こういう時に慌てて外に出た時を狙って、テロリストは本命の爆弾を仕掛けていたりするんだ。こっちは囮だってな。映画で見たぞ)
ニッキーの予想は外れた。起こっていたのはテロではない。
既に近くの教室から生徒たちが集まっていて、その人混みの間からニッキーは図書室の方を覗いた。
扉から本棚が倒れるようにして飛び出している。周囲はガラス片ばかりだった。
図書室からは、壊れた扉をくぐって生徒たちが出てくる。周囲の人たちに手助けをされて、ある者は泣きながら、ある者は激怒しながら救出されていく。
被害に遭っていたのは後輩である二年生の生徒たちだった。図書室から出てきた彼らは口々に「本棚が倒れてきやがったんだ。順番に全部倒れたんだぜ。俺は生きてるのか? 生きてるよな!」と事情を聞きに来た教師に喚いていた。
誰もが入口の割れたガラスで制服が傷ついており、一目で被害者かどうかの見分けはついた。
その内の一人、やたらと教師に状況を説明する生徒がいた。
その肌の黒い男子生徒には見覚えがあった。ニッキーの弟の友人、ゴルゴだ。
ニッキーと彼は弟を通じて話をする仲だったので、知らない顔という訳ではない。事情を聞けるかもしれないと歩み寄って「無事なのか、何があったのか」と声をかけてみた。
「ニッキー・マークス! ニッキー! やべえんだよ。こいつはダイハードの撮影じゃねえ。分かってやがるのか」
「分かってるさ。ダイハードだったら学校ごと吹っ飛んでるぜ」
ゴルゴは興奮した様子でニッキーの肩を叩くと、窓の破損した図書室を見るようにジェスチャーで促していた。
「棚がいきなりドミノみたいに崩れてきやがったんだぜ。本棚の間にいた奴ら、どうなったんだ」
それから、額から血を流している生徒や、抱き合って泣いている生徒たちで廊下は騒然としてきた。
立ち尽くしてその様子を眺めていたニッキーだったが、ふとある事に気づいた。
弟の友人であるゴルゴがここにいる。恐らくは授業で図書室を使っていたのだろう。今、丁度終わりのチャイムが鳴った。ということは、ゴルゴのクラスの生徒たちは皆、この中にいたことになる。
ニッキーの弟のラルフもこの事故に巻き込まれた……。
ゆっくりと図書室の方へと足が向かっていた。
中から誰かの叫び声が聞こえてくる。
「下敷きになってるやつがいる! 引っ張り出してやってくれ! 血が出てるんだ! やべえぞ。誰か救急にコールをしてくれ、頼む!」
誰かが負傷している。
その報告からニッキーは「弟に限ってそんな」という現実から目を背ける考えと、「被害にあったのは弟に違いない」という思い込みとが混沌と駆け巡っていた。
パニックを起こしかけて、現場をうろついている時だった。
急に肩を叩かれた。
急いで振り返ると、ニッキーの前には見慣れた顔があった。
「兄貴、ここで俺が死ぬなんて映画みたいなこと、起こりはしないぞ。何だよ、そんな亡霊にでも会ったような顔してよ」
兄の心配などよそに、ニッキーの弟のラルフは苦笑して立っていた。
イングランドのサッカー選手、デヴィッド・ベッカムのように髪の毛を真ん中だけ軽く立たせた金髪。角張った頬骨から強面の印象を与えるが、兄に向けて笑いかけるその表情にはあどけなさが残る。そんなラルフは学校指定のポロシャツの裾が少し破れていたが、あとはまるで無傷であった。
ニッキーはラルフの無事を知って安堵のため息をつきそうになるが、強がってそれを抑え、咳払いで誤魔化した。
「心配なんかしてねえよ。お前はダイハードに出てもプラトーンに出てもプライベートライアンに出ても絶対にくたばらねえだろうぜ」
するとラルフは聞こえるか聞こえないかの声で笑い声を上げてから、騒ぎになっている図書室を振り返った。
「いきなり倒れてきてよ。俺も間一髪だったんだぜ、兄貴。しかしよ、これは……」
ラルフは言い淀んだ。そして、連絡を受けて駆けつけた救急隊員が、生徒たちの無事を大声で確認し始めた。
そこから一歩離れた場所にニッキーとラルフは立っていた。ようやく心が落ち着いてきたのだが、ラルフがぞっとするほど暗いトーンの声でニッキーにだけ聞こえるように囁く。
「誰かが本棚を倒した。こんなことが普通に起こるとは思えない。なあ、信じるだろ、兄貴」
同意を求めるラルフのその目は、まるで映画の中の登場人物のように演技じみているが、必死さが伝わってくるものがあった。
その時のニッキーは肯定も否定もしなかった。
弟が無事だったという安堵感に浸って、それ以外のことは考えられなかった。
遠くからゴルゴがやって来てラルフと抱き合い、お互いの無事を確かめ合い、当時の状況についてを話し始めていた。
ゴルゴは救急隊員にもらったのか、オレンジ色のタオルを肩から被っている。彼らの会話の中に入らなかったニッキーは、突然起こった耳鳴りに悩まされながら立ち尽くすしかなかった。
やがて、タオルに包まれた何人かの生徒たちが図書室から隊員たちに背負われて出てくる。自力では歩けないのだろう。その事実がニッキーをさらに恐怖の中へと突き落とした。
突然発生したその出来事はネットニュースになった。州の新聞記者も学校に来て取材をし、一度だけ地方のテレビ局がニュースのためにカメラを回しに来た。
それだけの騒ぎになったのは、この一件で死者が出てしまったからだった。
不幸にも亡くなったのはエリス・キンブリーという女子学生。
ラルフとその友人のゴルゴの同級生だった。
ニッキーはネットニュースで知ったのだが、彼女は本棚の下敷きになってしまったらしい。倒れた書架は全部で十だ。その真ん中辺りの六つ目あたりで巻き込まれたと書かれていた。
フェイスブックを覗くとエリスの死を悼む同級生達のコミュニティが出来上がっており、様々な追悼の言葉が並んでいた。
「目立たない性格だったけれど気が利いて親切で明るい良い子だった。将来は物理の先生になりたいと言って勉強を頑張っていた」
「家は貧しかったようだけれど、持ち前の頑張り精神で奨学生での大学進学を目指していた。グループワークではトピックの中心にいることは少なかったが、必ず存在感を放っており、議論が脱線しそうな時はすぐに本題に戻すような力を持っていた」
などなど。
ニッキーはそんな書き込みを読みながらため息をついて、年季の入ったiPadの画面を暗くする。
自宅のリビングのソファーでニッキーは、隣の部屋でパソコンを前に何かをしている弟たちを見た。
今日は休日であり、ラルフは家に友人のゴルゴを呼んでいた。二人は数日前からパソコン上で何やら制作をしているようであった。ニッキーはそれを覗いてもさっぱり何をやっているのか分からなかったし、恐らく聞いても分からないので会話には加わらなかった。
図書室の一件からもうすぐに一週間が経とうとしていた。
巻き込まれて怪我をした生徒もいるらしく、死者が出たことで精神的にナーバスになっている生徒もいるようだ。しかし、少なくともニッキーの目の前に居る二人の当事者たちには目に見える影響はないようだった。
やがて、ラルフたちは数冊の本を持ってリビングの方へとやって来て、コーヒーを入れるとそれらを読み始める。
ニッキーはiPadで適当にニュースサイトを巡っていたのだが、いつの間にか隣にラルフが移動してきて座っていた。
「なあ、兄貴。ちょっとさ、自信が無くて話せなかったことがあるんだけどさ。こいつと話してたら、やっぱり兄貴にも相談した方が良いかもしれないってことになってさ」
「何だ。実は二人は付き合ってたみたいな話なら別にしなくても良いぞ。俺は分かってるからな」
そんなジョークを飛ばすと、ラルフは首を振って苦笑いしながら肩を叩いてきた。
まるでそれはここから話すことは決してそんな「ジョーク」が挟まるような余地なんてないと言いたげだった。
ラルフの態度に、ニッキーは襟を正すように座り直し彼の言葉を真剣に受けようとした。
「図書室の棚が倒れた事件。もうみんな事故だということにして、原因をこじつけでも良いから作ろうとしてるやつさ」
振られた話題にどきりとした。
「あれは殺人だぜ。不運な事故なんかじゃねえよ。計画的に仕込まれた『椅子取りゲーム』ってやつなんだよ」
にこりともせずにラルフは言う。
「殺人? なら、あのエリスって子は誰かに殺されたのか」
「こっち来てみろよ。ぶったまげるようなことが分かるぜ」
そう隣のパソコンのある部屋に呼んだのはゴルゴだった。何やらマウスを操作して画面を閉じたり開いたりしていた。
ニッキーは図書室での一件を事故としか考えていなかったので、まだ弟たちは何かの冗談に自分を巻き込もうとしているとしか思えなかった。
「数日前からフェイスブックを覗いてたんだが、ちょっと気になることがあってね。きっかけはこいつの冗談だったんだけど」
ラルフはフェイスブックの自分のページを呼び出すと、そこに書き込まれた無数のメッセージをツリー状に展開した。一つのトピックの下に何十個もの書き込みがあり、その下にさらに同じような返信がされていた。
「これは俺のクラスメイトだけが見られるやりとりさ。ちょっと呼びかけてみたら、この通りだ」
得意そうに言うと、ラルフが最初に投稿したと思われるトピックを見せてくれた。
「州立大学給費学生、繰り上がりで採用されているやついるよな」
そんなラルフの呼びかけで、目の前の膨大なツリーは出来上がっていた。この問いについて様々な反応がフェイスブックをやっているクラスメイト達から寄せられていた。中には「変な憶測をするな」とか「エリスの死を変な印象で騒ぎ立てるべきじゃない」とか、トピックそのものを批判するものも多かった。
「それは俺たちだってエリスのクラスメートだ。彼女の知り合い、友人、家族をいたずらに傷つけたくはないさ」
まるで、ラルフの言葉のタイミングはニッキーがコメントを読み終えるのを狙ったかのように正確だった。
「でもよ、兄貴。もしもこの件が誰かの手によって引き起こされたものだったら、そいつを暴かなきゃならねえとは思わねえか」
ラルフの目は座っていた。
トピックによって主張されているのは、「州立大学の給費学生」の件であった。
ニッキーたちが通う高校には二年生の段階で、州立大学への推薦がもらえるようになっていた。それも、卒業までの学費を州政府が負担してくれるというもので、家庭の事情から大学進学を諦めざるを得ない者にとっては願ってもいないチャンスになっている。
サクセスストーリーが眠っていそうだとニッキーは予感した。貧しいながらも勤勉に励み、大学へ進学して給料の良い会社に入る。まさに大逆転の人生だ。
そんな風に給費学生のモデルケースを思い浮かべていた。つい、他人をドラマに仕立ててしまうのが彼の癖だった。そのせいで被害妄想が激しかったり、安易に人を疑ったり、デメリットも多いが、誰かに対する共感は人一倍に持つことができた。
ともあれ、給費学生だが、学校から選ばれるのは成績優秀者の上位五名だった。その中にエリスも入っていたと言うのだろうか。
「エリスは五番目の成績で給費学生になれていた。ギリギリだな。本人もそれを意識してたんだろう。根を詰めてたようだぜ」
トピックに連なる意見の一つに、エリスが給費学生を意識していたこと、自分が五番目の生徒だと理解していたことが書かれている。ニッキーはそれを読んで少し考えてみた。
「さっきの『繰り上がりで採用されたやつがいる』ってのは、エリスが亡くなったことで新たに選ばれたやつがいるってことか」
ニッキーがぼそぼそと言うと、嬉しそうにラルフが答える。
「話が早くて助かるぜ、兄貴。そうなんだ。今日になって本人に通知があったらしいぜ。繰り上がりで給費学生になるぞって話がされたやつが」
「……なあ、まさかとは思うが、その繰り上がりで採用されたやつが、この事件を起こした。そう言いたいのか」
数多く並ぶ書き込みの画面を見ながら、ニッキーは言う。
すると、ラルフは隣に立っていたゴルゴと顔を見合わせて、おどけたように両手を広げて見せた。
「そう考えるのが自然じゃないか? こうして大勢の人間が賛同してるんだ」
「だとしても、決めつけるのは危険じゃないか。大衆は時にあてにならない。千人が賛成していても、一人の反対意見がまともだったこともある」
「それも兄貴、映画の話じゃないのか」
「そうかもしれないし、違うかもしれない。それに証拠もないじゃないか」
ニッキーが「証拠」という単語を用いると、嬉しそうに反応したのはゴルゴだ。
「証拠はないけどよ、それに繋がる証言はあるんだ。なあニッキー、俺たちはあの現場に居たんだぜ。ちっとは信用してくれよぅ。なあ?」
人差し指を何度か振ったゴルゴは、持ち前の人懐っこい笑顔を見せるのだった。
ゴルゴはニッキーとラルフの幼なじみだった。本人はいつも首から怪しげなチェーンのアクセサリーを下げて、腕輪やら足輪をつけて喜んでいるようなやつだが、家はニッキーから見ても恐ろしく厳格な家だった。
いわゆる食事の前と就寝の前には祈りを欠かさず、日曜の礼拝には家族で参加し、一時期は各家庭に聖書を配布して教会への寄付を呼びかけるような活動もしていたらしい。
そんな家庭で育った反動なのか、ゴルゴはやたらと神とか奇跡とか運命とか、そんな言葉に反抗的な人間になっていた。
時々、ニッキーはラルフとゴルゴと一緒にテレビでバスケットボールの試合を観ることがあった。
応援するのは地元ニューヨーク、ブルックリンを本拠地とするニックスだ。あの伝統的な白のユニフォームをまとって躍動する選手達を見ながら、三人で一喜一憂していた。
そんな時でも、例えば神に祈りたくなる場面、ニックスがフリースローを与えて逆転の危機を迎えているような瞬間でも、ゴルゴは祈らない。
彼は口癖のように言うのだった。
「こんな時にばかりに頼られても、『ニイちゃん』は困っちゃうぜ」
『ニイちゃん』というのはすなわち「兄ちゃん」であり、それはすなわちイエス・キリストのことであるのだが、ゴルゴは親しみを込めてそう呼ぶのだ。
ゴルゴは自分が図書室での事故から無傷で生還したのはただ単に運が良かったと考えていて、決して彼の中の『ニイちゃん』が助けてくれたわけではないと思っている。
そして、この事件を起こしたのも『ニイちゃん』の気まぐれなどではない。ゴルゴなら必ずそう言うだろう。
「窓際の一番奥にいたぜ。この時間は必ずここで画面とにらめっこだよ、やっこさん」
ニッキーはゴルゴのささやきを聞いてから、目線を部屋の奥へと持って行った。
図書室の事故がただの事故ではなく、故意に引き起こされた「事件」である。そんな大胆な意見を聞いた翌日だった。放課後に三人は集まると、校内のパソコンルームに来ていた。
この部屋には放課後、パソコンを使うクラブ活動の生徒がいる。それでも部員数はそれほど多くないと言うか、片手で数えられるほどなので、多くの席は空きとなっているのだ。
その場所は自由解放になっているので、誰が使っても咎められることはなかった。
ニッキーは奥に座っている生徒を観察した。
黒縁のメガネは生真面目な学生を思わせるのだが、髪の毛は金髪を逆立てていた。その点はラルフと同じだったが、メガネの男の場合はその度合いが少し違った。まるで何本も棒が突き刺さっているように尖らせていたのだった。口をへの字に曲げて眉間にはカルフォルニアバレーのような深い堀がある。
第一印象が「気難しそうな男」だった。
ニッキーは彼を見ながら、昨日、ゴルゴに言われたことを思い出していた。「証拠はないけれど、証言はある」。どういうことだろうかと、様々なドラマを夜通し頭の中で繰り広げているうちに、昨晩は寝てしまっていた。
それを通してニッキーが導き出した結論は、「ゴルゴがこの図書室の事件の犯人について、目星をつけている」というものだった。
「行こうぜ、兄貴。ゴルゴ。俺から話してみるぜ」
ラルフは迷いなく奥へと進むとパソコンの前に座ってる男に近づく。
「ようやく話しかけてきたか。何なんだよ君らは。数日前から入り口でうろちょろされると、気が散るんだけどな」
深いため息と不平に迎え討たれ、ラルフは舌打ちをする。
「何を考えてるのか分からないが、時間がもったいないとは思わないのかね。これを見たまえ」
男は左腕を捲って腕時計を見せてきた。デジタル式のその時計は時刻ではなく、ストップウォッチになっており、現在は停止しているようだった。
時間は一時間と二十三分を示していた。
ボタンを操作してそれをゼロへと戻すと、時計を隠すのだった。ニッキーは彼の腕の右にも時計が巻いてあるのに気がついた。
「君らが僕を監視してた時間だ。一時間三十分あれば映画が観られるぞ。どうだ、後悔してきただろう」
すかさず映画好きのニッキーが口を挟む。
「映画は大抵二時間だから少し足らないな。一時間半のもあるけれど限られてる。昔のになるほど短くはなるけどね」
「それは失礼。そういうことを調べる時間にも使えた訳だ」
「ふん、お前のような殺人犯にお説教はされたくないぜ、ギルバード」
会話が映画の所要時間という話題に入って、弛んできた時だった。
ラルフはギルバードと呼んだ時計の男を、何のためらいもなく、いきなり、稲妻のように「殺人犯」呼ばわりしたのである。
「お、おい。やめとけよ、そんないきなり」
ニッキーは怖気づいて、つい二人の間の仲裁に入ってしまっていた。
確かにゴルゴとは「例の図書室の件で怪しい奴がいる」という話をしていたが、あくまでそれは「噂」の域を出ない程度のことだったはずだ。それをいきなり相手を「殺人犯」と決めつけるのは早計であるし、非常識極まりない。
ただ、ニッキーは弟の性格ならばこうなるのも僅かながらは納得できた。
弟のラルフは小さい頃から危なっかしくて見ていられなかった。誰かが見張っていないとすぐに危険な行為に出る。
二人がまだ幼い時、父親の近所付き合いの道具として、草野球のチームに入れられていたことがあった。
そこでラルフは投手を務めたことがあったのだが、相手のチームの一番の強打者にデッドボールを当てたことがある。相手は負傷してベンチに下がり、試合はチームが勝利したのだが、後にラルフは半ばわざと出した死球だったとニッキーにだけ自白したのだった。
もちろんわざとだと分かれば、草野球のチームから追放される可能性だってあった。小規模とはいえ、グラウンドの周りの家の人たちや、家族も応援にくる。それなりにちゃんとしたチームなのだ。
しかし、ラルフは誰にも悪びれずにニッキーに本心を告げた。「相手は避けようと思えば避けられたよ。それに四球出すより球数も節約できたしね」。
そんな突拍子もないことを言い出したり、実行し始める弟をニッキーはいつでも心穏やかに見ていられなかった。
それでも見捨てる訳でもなく、いつでも側にいて何かあれば味方になってやりたいと思っていた。
だが、積極的に彼の無茶に付き合うような度胸はない。
だからこの時、弟が誰かを「殺人犯」と言い放っても、追従して賛成するようなことは出来ず、はらはらしながらその行方を見守るので精一杯だったのである。
パソコンに向き合っていたメガネの男、ギルバードと呼ばれた彼は、渋い表情を一つとして変えずに左腕の袖を捲る。そして、ストップウォッチを操作するのだった。
カウントアップが唐突に始まった。
「君らのことはよく知っている。ラルフにゴルゴ。学業成績は真ん中あたり、そして常につるんで学外で散々悪行を働いているそうじゃないか」
ギルバードはまるで教師のような立ち居振る舞いで述べた。
「人を殺すまでのことはしてないぜ。自分が死にそうなことは何度かあったけどな」
それは弟なりの皮肉だろうが、全く目は笑っていない。ギルバードも同じく仮面を被っているのではと思われるほどに表情を変えなかった。
「ギルバード。お前がエリスを殺した。でたらめなんかじゃないぜ。根拠もその動機も揃ってるんだ」
またしても率直に言い放っていた。言葉の一つ一つにニッキーは怯えるようだった。自分に向けられている訳ではないが、その向こう見ずな弟の言葉は危なっかしくて、事態を静観できない。
「まず、お前はエリスの次に大学の給費学生に選ばれていた。それを教師から告げられていた。その証拠もあるんだぜ」
ラルフはポケットからスマートフォンを取り出すと、画面をここにいる人物たちに見せるのだった。
「給費学生の成績リスト……?」
それはパソコンの画面をカメラ機能で撮影したものであった。表計算ソフトで作成されたシートに生徒の名前が書き連ねてあり、そこに成績と順位が表示されている。
名簿には六人の名前が見える。恐らくこの画像の下の方にも生徒の名前は出ているだろうが、上手く外して撮影されているのか、それとも編集されているのか、とにかく六人しか名前は確認出来ない。きっとこの一週間、ラルフたちはこういう証拠をパソコン上で集めたり、犯人に突きつけるために編集したりしていたのだろうな。
この中の上位五人が給費学生として州の支援を受けて大学に通えるらしい。
ニッキーが目を細めると、五人目には確かにエリスの名前があった。
そして、そのすぐ下、六人目に記されている名は「ギルバード・ハーバー」。腕時計を二つ巻いている目の前の彼だった。
確かにこれを見ると、五人目のエリスがいなくなれば六人目のギルバードが繰り上げで給費を受けられる。
「給費学生の締め切りは一ヶ月後だ。そして、先月、ほとんど最後の評価の機会となるテスト期間が終わった。ギルバード、お前はテストの点数が悪かった。だから、このままじゃエリスに勝てないことを考えて、殺したんだ」
断定口調をラルフは崩さない。
流石にその話の流れはおかしいとニッキーでも思った。
もちろんギルバードは反論してくる。
「エリスじゃないても良いのでは。上位五人の誰か、誰か一人でも消せば繰り上げになるが」
「ギルバード、お前はエリス以外の選出者を言えるか?」
そこでギルバードは初めて顔をしかめる。
すかさずゴルゴが会話に入ってきた。
「知らないだろうなぁ。お前はテストが終わって担任に呼び出された。その時に話があったはずだろ。『お前の成績じゃ給費生は無理だ。惜しかった、惜しかったぞギルバート。あとはニイちゃんにお祈りするかー、黙って就職するかー、とにかく考えてくれよな』って感じによ。んで、自分が滑り込めずにギリギリでアウトになったことを知る。でも、知ったのはそこまでだよなぁ? 選出者については知らされなかったはずだぜ」
「そうだ。俺たちは他の選出者に聞き込みもした。証拠のムービーもある。選出者たちは、他の選出者の情報を全く知らなかった。けれどな、ギルバード。お前は給費生を諦められなかった。だから、こいつに話を聞いたんだ」
ラルフは言い終えてから一つのムービーを再生し始めた。画面にはなで肩でメガネの男が映っている。
彼は食堂かどこかでラルフたちとインタビューじみた会話をしており、その中で聞き逃してはならない言葉が出てきた。
『そうだな、やたらギルバードはパーティでの会話にこだわってたな。多くの人にさりげなく聞いてたみたいだぞ。給費学生のことも、その時に聞いたんだろうぜ。俺がサプライズで用意したケーキのことも話したぜ。おっ、お前も聞くか? 家の事情でブルックリンから離れなくてはならなくなったエリスが、いかにこの街を愛して、両親に争い、そして猛勉強の末に給費学生になったかを……』
嬉々として話す、浅黒い肌の男が映像には映っていた。彼が何者かは分からないが、ニッキーは何となく違和感があった。その正体を確かめられないまま、続くラルフの主張を聞くことになった。
「こいつはエリスの知り合いで、三年生のゲイリーってやつだ。ゲイリーから聞いたらしいじゃないか。そう聞いたぜ。なあ、どうなんだよ」
「そんなお調子者は知らん。ゲイリーなんて名前も聞いたことはないな」
ここで初めてギルバードがラルフの言うことを否定した。
「おーっと、その言い逃れは出来ねえぜ。写真もあるんだ。ほれ」
すると、すぐさま差し向けるが如く、ゴルゴがスマートフォンを滑らせてきた。
表示されているのは、一枚の写真である。
そこにはパーティ会場らしきところで、先ほどの浅黒い男、ゲイリーと話すギルバードの姿があった。どうやらエリスがケーキを食している場面を写したものらしいのだが、その背景にしっかりと横向きのギルバードと、同じくゲイリーが写り込んでいた。二人はジュース入りのグラスを手に何かを話し込んでいるようだった。
「これは……」
ギルバードは驚いたように声を上げる。
「これだけじゃ、何を話してるのか分からないだろう」
「お前はこのゲイリーを知らないって話したろ。それは嘘だったわけだな。このパーティーで話してたんだからな」
ラルフが指摘するとギルバードは目を細めて今一度、その写真をあらためていた。
「こいつの名前はゲイリーなのか?」
「とぼけようとしても無理だぜ。証拠は上がってるんだ。ははは、観念しろよ。何ならこいつに話を聞いてみるかよ。それとも、ここに呼んでみるかー?」
「いや、それは時間の無駄になるだろう。そいつは俺を知ってると言い、俺はそいつを知らないと言わせてもらう」
「それならこの写真は何なんだ。合成だとでも言うのかよ」
ラルフが問い詰めると、ギルバードは暫し考えるような表情をしていた。
先ほどからすっかり場から追い出されるようにして、話の中心から弾き出されたニッキーだった。今は三人のやり取りを息を飲んで見守っていた。
ニッキーの周囲の人間は皆、あの図書室での件は事故だと結論していた。
だが、その一方である疑問も共通して抱いていたのだ。
本棚が次々に倒れたということが起きるとしたら、どんな「事故」なのだろうか。
地震がその日に起きたという報告は、どこからもされていないはずだった。何かのバランスを崩して本棚が倒れる。それは決して「自然に起こった」ことではないような気がしていたのだ。
だとしたら、やはりこの事故は人為的なものが働いた「事件」なのだろうか。
「さっきのビデオの人物と、この写真の人物は別人じゃないのか。今から確認しに行くのは、時間の無駄にはならないだろう。どうだ?」
ギルバードはニッキーが抱き始めた疑いを振り払うかのように、冷静に告げるのだった。
「それで納得してくれるんならいいけどよう、後になって言い訳しないでくれよな」
ゴルゴが答えて四人はパソコン室を後にする。
彼らの通う高校はブルックリン区の図書館の側にあり、景観が昔ながらのヨーロッパ風のアメリカ建築であったために、観光客達がこぞって写真を撮りに来る。学校の門の側でカメラを操作する人々を、廊下の窓から見る。ニッキーはその人達がどの国からやって来たのかを考えていた。アジア人風だったので中国か日本だろうか。
移動してたどり着いたのは三年生の教室だった。ニッキーの隣のクラスであり、そこにはまだ多くの生徒が残っていた。
ニッキーは昨日、学校のクラスメートたちで作るフェイスブックのページを見ていたので、この場で来週に行われるハロウィンについての話し合いがあるのを知っていた。エリスの件があって自粛する空気もあったのだが、「暗くなって萎んでいるばかりじゃ、この先何年経ってもハロウィンの季節が来る度に鬱々してしまう。ここは目一杯楽しもう」という誰かの書き込みによって空気は一変して、こうしてハロウィンに向けて何か催し物を始めようと話し合いが行われているのだった。
ゴルゴが先頭になって入って行くと近くの女子生徒に事情を話して、ゲイリーの所に案内してくれた。
確かに、少なくとも、ニッキーたちが直面したのは、ビデオに出演していた男子生徒そのものだった。ゴルゴは彼と握手をしてからニッキーたちを一瞥して「何事だ」という顔をしていた。
そこでスマホのムービーを音を消したままで見せて、「この前のインタビューだぜ。これに出てる本人が本当にゲイリーかって、変なことを聞くやつがいてよ。んで、会わせてやろうって話になったんだよ」とゴルゴが伝えるのだった。
すると、ゲイリーは首が取れてしまうのではないかと思われるくらいに頷いた。
「これは確かに俺だぜ。男前に撮れてるだろう? ははは。また何でも聞きたいことがあったら来いよな」
そんな風にゲイリーは告げてくるのだった。まるでブルースでも歌っているかのように、どこかもの悲しいしゃがれ声であった。
またしても違和感が走る。
ニッキーはゲイリーの態度と、そしてスマホの動画のゲイリーの姿に何か不自然なものを感じていた。
写真の方も確認は取れて、これでギルバードがエリスを殺害する動機は揃ったことになった。
「これで決まりだな。エリスを殺したのはあんただ。これから誰かに話して警察に突き出してやる」
四人で教室から出て扉を完全に閉じてから、ラルフが宣言する。
「おいおい……ちょっと待ってくれ。早急すぎるぞ。確かに動機はあるかもしれないけれど、まだ証拠がないだろ。どうやって図書室で殺人を行ったって言うんだ。それが分からないうちはまだ」
「兄貴は弱虫だ。こいつが悪いことは全て分かったんだ。犯罪の方法? 証拠? そんなものは警察で話してもらえば良いじゃないか。自白させるんだよ」
突然、ラルフに牙を向けられてニッキーは何度か瞬きをした。滅多に弟と喧嘩をしない彼だったが、時折、一年に一度くらい、本気で弟を怒らせてしまうことがある。その時のような反応をラルフは見せているのである。
しかしながら、いつもの怒りとはどこか違っている。感情に全てを委ねるような態度ではない。発露しているのは怒りの気持ちだけではない。何かが混ざっているのだ。ニッキーはラルフの言葉を真っ直ぐ受け止めたのだが、その正体は掴めなかった。
ニッキーとラルフがにらみ合っていると、割って入ってくる声があった。
その人物は左腕のストップウォッチを停止させてすぐさまゼロに戻す。
「今まで数えてきた時間をすっかり無駄にすると思ったが、事情は変わった。どうやらこの件は本当に事件のようだな」
ギルバードがニッキーたちを見回してから冷静な口調で言うのだった。
どうして自分が犯人だと目されており、なおかつ追い詰められる立場であるはずなのに、ここまで落ち着いていられるのだろうかとニッキーは疑問に思う。
「認めるのか、認めないのか。それだけ聞かせてくれ。あとは、それこそ本当に『時間の無駄』だからな」
「まだだ。俺がもしも万が一、何があってもそれはないのだが、犯行を認めるのだとしたら、この謎が解かれた時だ。『どうやってエリスは殺害されたのか。そして、その証拠はどこにあるのか』。この疑問が解消されない限り、誰が犯人であったとしても、そして例え事故であったとしても、誰の納得も得られないぞ」
思わずニッキーは頷いてしまっていて、ラルフから睨まれることになってしまう。
確か家では「ギルバードが犯行に及んだ証拠はない」とラルフは断言していなかったか。ニッキーは思い出していた。それならば、犯罪は立証できないままになってしまう。
だとすれば、ギルバードは無実でなければならない。
きっと百の怪しいと思える状況証拠を積み重ねてみても、物的な証拠が出てこなければ、もしくはギルバードに優位な物的な証拠が出てくれば、その場で彼の無実が確定する。必要なのは確実な物的証拠のみなのだ。
証拠という言葉に、まるで眠ってしまったかのようにラルフは沈黙してしまっていた。
頼りとなるのはゴルゴだけだったので、彼の言葉を待つと、いつものようなふざけ半分といったような声が返ってくる。
「もちろんその辺も抜かりないぜ。ただなあ、今は図書室には出入りが制限されているだろう? どうしたもんかなあ。図書室に入れてもらえれば、全部つまびらかになるんだかなあー」
「その、わざとらしい誘い文句、気色が悪いぞ。言いたいことは分かった。要するに、図書室に忍び込めればいいんだろう」
「話が早くて助かるぜー。そうだなあ、夜なんてどうだ? 明日は休みだぜ。それとも、エリスから奪った席を守るのに勉強で忙しいかなあ?」
「変に挑発しなくてもいい。こちらは逃げ隠れしないぞ。時間を合わせるか」
ギルバードは律儀にもメモを懐から取り出して、ゴルゴと待ち合わせの時間を書き留めているようだった。
夜に図書室に忍び込むつもりらしい。
そんな映画みたいな非日常への誘い、ニッキーの胸が踊らない訳はなかった。事態が事態で不謹慎であるとは自覚していたが、自らの興味は奪えない。
「図書室は封鎖されてる訳じゃないんだよ、兄貴。ちょっと鍵がかかってるだけなんだ。だから、ぶっ壊して今すぐにでも入れば良かったんだ」
縦長の缶に入ったカフェインを多く含む清涼飲料をあおりながら、ラルフは繰り返し文句を述べていた。
「そういうこと、あまり外で言うなよ。疑われるだけじゃ済まねえぞ」
その隣で缶コーヒーを飲み終えたニッキーが独り言のように言った。
ゴルゴとは夜に会う約束をして別れ、ニッキーとラルフは帰宅の途についたのだが、その最中もラルフはタイマーの切れない目覚まし時計のように話し続けるので、たまらずニッキーは近くの公園へと彼を誘導し、そこで思う存分に毒を吐かせることにしたのだった。一度彼の主張が終わって、怒りは収まったかと思うと、再び噴出してくる。その繰り返しだった。
「ギルバードを自由にしたことの方が重大な問題だ。あいつは殺人犯だぞ。野放しにしとけば、証拠を隠すかもしれねえ。なあ、兄貴。そうなりゃもう事件は迷宮入りなんだぞ。後になってこの選択が全ての間違いだって気づいても、何もかも遅いんだぞ」
「でも、ギルバードは約束した。今日の夜、図書室に来るんだから、それで良いじゃないか」
これもまた何度となく告げた言葉だった。
二人の後ろを自転車が通り過ぎた。
この公園は港に接しており、観光客も数多く見られるような景観の美しい場所だった。ニッキーとラルフは港に接する丘の、仕切りとなるフェンスに寄りかかって話している。
落ちかけている陽が水面に光をいっぱいに広げて、建物の影となっている場所まで手を伸ばしていた。
遠くからストリートバスケをする少年たちの声が聞こえてくる。五、六人のうち二人くらいはニューヨークニックスのTシャツをデザイン違いで着ている。それを見ると、ニッキーは呟いた。
「今日はバスケ観られそうにねえな。あの四番のセンター、名前なんて言ったかな。怪我から今日帰ってくるらしいぜ」
ラルフはその言葉を聞くと、目元の辺りを押さえて、何か言いかけた口を一度閉じると、そこでようやく不平を吐き出すのを止めるのだった。
ボールがリングに跳ね返される音がやけに大きく聞こえて、今度はニッキーから話を切り出した。
「お前はこの事故だか事件だかに巻き込まれたから、俺なんかとは意識が違うんだろうけどさ。それにしたって、ここまで首を突っ込む必要があるのか?」
「兄貴は気にならねえのかよ。ギルバードを許すのかよ」
「そういう訳じゃねえんだ。どうして俺らがこんなことをしなきゃいけないんだってことだ。何だったら警察にこれまでの話をすれば、本当のことが分かるかもしれねえ」
ラルフは俯き加減になって押し黙ってしまう。
彼も警察を信じていない訳ではないのだとニッキーは思っていた。
第一、この出来事には不可解なことがある。
本棚の下敷きになって亡くなった少女がいて、その棚が倒れた原因がまだどこからも発表されていないのだ。
事故なら事故で、目撃証言なり自供なり、どこからか話が漏れてくるのが普通だろう。騒いでいて本棚を倒してしまったとか、棚が脆くなっていて崩れてしまったとか、そういう説明が出てくるべきなのだ。
しかし、未だに真相は明らかになるどころか、見解さえ確かなものが出てきていないというのが現実だ。
ニッキーは警察もきっとこの事故に何か引っかかりを感じて捜査をしているに違いないと考えていた。
だからこそ、警察の発表を待ちたい。待つべきだというのがニッキーの意見だ。ここで自分たちが積極的に首を突っ込んでいく必要はない。
ラルフもそれくらいは分かっているだろう。
そう思うからこそ、ニッキーは弟の切羽詰まったような行動の数々に疑問を抱くのだった。
あくまで捜査は警察に任せるべきだ。病気は医者に、機械の故障は機械のメーカーに頼むのが効率的だ。そう言わんがばかりに告げた言葉に、ラルフは唇を噛んで何も言わなかった。
もどかしげに清涼飲料を流し込むと、「バスケはネットでハイライトを観ればいいさ。とにかく夜だよ、兄貴。ギルバードが来なければそれだけであいつの弱点が増えるから、俺たちは行かなきゃ。あと、四番のセンター、名前はサンダースだ。俺はあまり期待してないけど、今日の試合は活躍する気がするね」と早口で告げて地下鉄の駅へと向かっていくのだった。
深夜に外出するために僕らは寝室の窓から長めの脚立を使って抜け出す。そして、自転車でいつもの登校の道のりより倍の時間をかけて、夜の校舎へとたどり着いた。
すでにゴルゴとギルバードは閉ざされた校門へと集合している。面々が揃ったのでいざ図書室へ、となったのだが、当然のことながら門は閉まっている。無理に乗り越えようとすれば、何らかの警報装置が作動して痛い目をみるだろう。
ニッキーはどうしたものかと考えていたが、その点についてはゴルゴが全ての解決策を持っているようだった。
「こういうのは『ニイちゃん』の裏をかくんだよ」
そう述べたゴルゴは校舎に面している廃ビルへと一行を案内し、二階の割れた窓を開けた。すると、ちょうど校舎を囲む鉄柵の頂点が見える。
「乗り越えるだけが壁じゃねえのさ。なあ、『汝、道が開かれぬ時は道を疑うべし』」
ゴルゴのその言葉は聖書の引用かもしれないし、そうでないかもしれない。どうあれゴルゴは近くにあったトタンを何枚も柵の上に重ねると、即席の橋のようなものを作って夜の校舎への道を作るのだった。
誰一人何も話さなかった。足音が響き、件の図書室が見えてくる。扉には鍵がかかっていたが、ゴルゴが懐から鍵を取り出して解錠した。
「お前らと別れた後にちょっとな。全くよう、今日で一学期分の勉強をした気分だ。教師の一人に『前回のテストで分からないところがある』って話したら、喜んで夕暮れまで教えてくれたぜ。何でも俺は『やればできる生徒』なんだそうだぜ」
ゴルゴははしゃぐように言うとするりと鍵を回して、皆を室内に案内するのだった。
つまり、ゴルゴは鍵を手に入れるためにわざと職員室に行って勉強を教わるふりをし、そのまま自由に動ける機会を窺っていたということだ。これには少し教師が可哀想に感じた。確かにゴルゴはニッキーからすれば十分に勉強ができるし、本腰を入れて取り組めば給費学生になることも非現実的な話ではない。そんな生徒がやる気を見せてくれたとしたら、教師とすれば張り合いを感じることだろう。
そんなことをニッキーは考えつつも、無音の図書館に足を踏み入れた。
すると、何かの電子音が聞こえた。ニッキーの隣でギルバードがストップウォッチを操作している音であった。
「時間のことなんて気にしていられるのかよ」
「それなら俺は十五分したら一人でここからお暇させてもらおうか」
ギルバードが述べるところによると、今日もおそらく当直の教師はおり、夜間の見回りも予定されているだろうということだった。
見回りの頻度だが、流石に一時間に一回ということはないだろうし、一晩に一回というのもないだろう。だが、その見回りの教師に発見される確率は、結局のところ滞在した時間が長ければ長いほど高くなる。
そんな当たり前の理屈から、ギルバードは十五分という制限時間を設けたらしい。
彼のそんな講釈を聞くと、ニッキーだけでなくラルフやゴルゴも納得して従うことに決めたようだった。
「それでは手短に、かいつまんで、お願いしようか。この本棚の謎を」
ギルバードが、倒れたままになっている本棚の横に立って言った。
「十五分かー、十五分ならジョークを混ぜてる暇もねえなあ。仕方ねえ、んじゃ僭越ながら推理を披露させていただこうかね」
軽やかな口調と共にゴルゴは本棚の近くに移動すると、皆を手招きで集めるのだった。
「こんな感じでよ、本棚はドミノ倒しよ。一番後ろのを起点にして、ドカドカドカって倒れてって、ガシャン」
本棚の倒れていった先をゴルゴは指差した。そこには廊下の窓ガラスを突き破って上半分が外に出ている棚があった。
「その倒れた本棚の真ん中あたりにエリスがいたんだなぁ。不幸かも知れねえが、それだけで片付けられない奇妙なことがあるんだわ」
ゴルゴは不敵に笑って本棚に近づいて、その一番後ろの棚の側でしゃがみこんだ。
辺りにはまだ本が散乱しており、事故当時の状況をなるべく保持しようとしているようだった。
倒れた本棚の中で残っているのは、一番後ろの一つと、その次と次の二つ。そこからはおおよそ三つほどの本棚のスペースが空いているが、おそらくここにエリスが挟まれた本棚があったのだろう。そこからさらに二つの本棚がしなだれかかるように倒れており、最後の一つが窓を突き破っていた。
落ちている本を踏まないようにしながらニッキーはゴルゴの側へ行く。ここで一人、人が亡くなっていると考えれば、不気味になってくる。
その思いはラルフやギルバードも同じようで、ためらう様子を見せつつも、ニッキーに続いた。
「この本棚はよう、確かに背も高いし巨大で、押し潰されたらひとたまりもねえ。でもよ、みんな疑問に思うんじゃねえか? この、最初の本棚。これを倒すのにどれだけの力が要るのかってな」
ニッキーの説明を聞きながら本棚を観察する。
彼の言う通り、棚はニッキーの背よりも高く、木製で厚みもあった。押し潰されればひとたまりもないだろう。
そして、誰もが何度も抱いていたであろう疑問。
これをどうやって倒したのか。
「聞くところによれば、本棚にもろに挟まれたのはエリスだけということになる。他に怪我人がいないんでな。そこから、分かるのはよ、倒れた瞬間を知るのはあいつだけってことなんだ」
「残り十三分だ」
ギルバードの冷静な言葉が場に投げかけられる。それはまるで、一気にゴルゴの説明通りに話が進んで、その勢いで推理の粗が見逃されることに警告を発したかのようだった。
「こう思わねえか? 倒すのはエリスを挟んだ一つだけでいい。エリスが本棚に入った瞬間に、それだけを倒せば全てがうまくいくんだ」
「なら、倒れた残りの本棚はカムフラージュか」
素早いニッキーの断定にゴルゴは頷いていた。
「それならエリスを挟んだその一つの本棚を倒して、それから他の本棚も倒してって、そんなことしてたら見つかっちまうぜ」
ニッキーの疑問に答えるのはまたしてもゴルゴだ。
「そうだな、ニッキー。ははは、それにな、これまた変な話だが、本棚を倒したやつを誰も目撃してないらしいんだ。エリスを潰したやつはおろか、これ全部、勝手に倒れたってみんな言い放ってんだぜ」
両手を広げて大げさに説明するゴルゴの様子は、まるで舞台役者だった。
「となると、誰かが押したわけじゃねえ、それなのに本棚は倒れた。これは『ニイちゃん』の仕業じゃねえのか? なあ。だから、この事件はこれまで捜査が止まってきたんだと思うぜ。目撃者が誰もいねえ」
ニッキーが何度も頭の中で思い描いた疑問が、今ここに再現されようとしていた。
本棚の倒壊。それが本当に偶発的に起こったと言うのだろうか。
クラスメートたちは皆、警察との面談をしたという。ニッキーもその場にいた近くの人間だったからいくつか質問をされた。事件発生時にはどこにいたのだとか、怪我の具合について聞かれたが、ニッキーはほぼ正確に自分の行動を話して、捜査員から「びっくりするぽど君は無関係だな。無関係オブ無関係だ」とよく分からない評価をされていた。
それはともかくとして、ニッキーはともかくとしてラルフのクラスメートたちから何の情報も得られていないというのは信じ難かった。
ニッキーはつい脅迫を疑ってしまうところだった。クラスメートたちは何らかの秘密を共有しており、誰もが共犯である。クラス全体が犯人という展開は何かの映画で観たことがあった。
「クラス全体が示し合わせて目撃者を隠してるっていうのは、どうかな」
ニッキーが言うと、ゴルゴは嘲笑うわけではないが楽しげな笑みを浮かべて返すのだった。
「その映画のような話。さすがはニッキーだぜ。脚本家にでもなるといい。でもよう、俺とラルフもクラスメートだ。そういう『示し合わせ』みたいな話は聞いたこともねえし、もしも、エリスが皆から嫌われていたら、あんな給費生のお祝いパーティをしたり、こうして俺らの捜査に協力したりするだろうかな」
ニッキーはゴルゴに見せられたパーティの写真を思い出していた。あの時の、誰もが心から喜んでいる笑顔が作り物だとは思いにくい。
「時間もねえだろうし、続けようぜ」
「残り九分だ。そろそろ足音が聞こえ始めてもおかしくないな」
「脅かすなって、ギルバード。そうだな。ここからの推理はラルフに任せるとするかな。時間を気にしながら話し続けるってのは、どうにも苦手でよう」
ゴルゴはおどけたように言うと、仏頂面で立っているラルフの方を見やる。
「推理はこうだ。犯人は後ろから本棚を倒したんじゃない。前から本棚を引き倒したんだ」
腕組みをしたままでラルフは言った。まるで、ここで話が振られることを分かっていたような落ち着きようである。
「前から引いた? でもよ、前からだったら、犯人も挟まれるぜ」
「ああ、違うのさニッキー。前からってのは、本棚の前からってことじゃないんだ。いや……いいのかなあ」
ゴルゴがすかさず反応するけれども、ラルフが片手の平を見せて「俺が話すから」と説明を引き受ける。
「いいか、兄貴。前からって言うのはよ、本棚を前からって意味でもあるけれど、ドミノ倒しを前から行ったってことなんだ」
ドミノ倒しを前から。
その言葉から連想した光景は、一番前の本棚を倒すことが後ろの本棚の倒れる原因となる……というものであった。
いや……それでは「ドミノ倒し」が成り立たない。どうやったら前から倒れていく棚が後ろの棚を押し倒すような原因となるのだろうか。
そんな風にニッキーが考え込んでいると、ゴルゴとラルフは倒壊した本棚の先頭、ガラスを突き破っているものの側へと歩いて行く。時間ももうないという意識はどこかへ行っていて、今は彼らの推理を理解したいという思いが強い。
ちょうど映画のクライマックスで時間を忘れてしまって画面に食い入る時の感覚に似ている。
「ガラスが割れたというのがなあ、このトリックの肝になってるんだぜ。いいか。棚の上の方にはどれも本が入っていねえんだ。例えば、この棚は作者の頭文字がEからIまでのものになってるよな」
先頭の本棚にはインデックスとなるプラスチック製の細い板が取り付けられていて、そこには「E~I」という文字が見える。
「ここらに散らばってる本、どうだ? Eの作者の本なんてねえだろう?」
調べてみると確かにそうだった。本棚は傾いていたが、壁にめり込むようにして先頭のものは中途半端な角度になっていたので、まだ本が残っている。しかし、どれもがFないしはGの作者、そしてわずかにIの文字が名前に入っている著者たちの本ばかりだ。
「で、来てみろや。どこだったか、ラルフ? 本を隠すなら本の中っていうけどなあ」
ゴルゴは一行を手招きし、肝心の場所をラルフに尋ねていた。すると、迷う様子なく彼は動き出して案内するのだった。
図書室のカウンターの側にあった、二段構造のカートに本が積まれている。本来、この四輪の使い古された感じのある台車は返却された本を一時的に保管しておき、それから時間を見つけて担当の者が本棚まで移動させるためのものだろう。
それが一杯になっているというのが、既に違和感を覚えさせる光景であった。
まるで何かの「置き場」となっているかのようであった。
ニッキーにも大方の話の筋は見えたのでカートの中身をあらためてみると、そこにはEから始まる著者の本が見つかった。さらに同じように特定のアルファベッドの作者の本が固まって納められているようだった。
調べてみると、このカートに存在している本達はどれも倒れた本棚の上の方にしまわれていなければならなかったものである。
「犯人は本棚の上部をわざと空けた。そして棚の横の仕切りへロープを巻いたんだ。今回倒れた全てのものにだよ。授業の前に全て空にしておいたんだろうな。それから一本のロープを綺麗に通しておく。そうしたら準備完了だ」
ラルフがそう説明すると、段取りよく今度はゴルゴが話の続きを引き継いだ。
「そこでギルバード、お前は確かエリスに本を探しておくように頼んでいたよな。友人から聞いたんだぜ。授業で同じグループだったお前に、アメリカの重工業の歴史について探すように言う」
まるで歌でも歌うように上気しきったリズムでゴルゴが述べ続けていく。
それはまるで映画の終盤で主人公が名演を披露するパートのようだった。
「これだぜ。あの時の図書室での授業は、各グループに別れて調べ物をするってやつだ。俺とラルフはよう、アメリカの建国の父たちについてってやつだ。ま、一種の『ニイちゃん』だぜ。それはどうでもいいがよ、お前は直前にエリスに頼んだだろう。『J』から始まる作者の本を。これが証拠さ」
ゴルゴは楽しそうに笑いながら懐から紙を出して、スマートフォンの灯りでそれを照らした。「グループ学習のまとめ」と書かれた紙である。それが何か分からなかったのでラルフに聞いてみると、何やら思い出すような仕草をしてから、「一人に一枚配られたんだ。まとめて個人でシートを作成してそれを教師が集めて採点する」と口調があやふやなのが気になったものの、ニッキーはその説明で満足して話の先を促していた。
「それが証拠?」
「これは間違いなくエリスのプリントだ。ここに書かれているのは、参考にするべき本のリスト。それがグループ全員のプリントに書かれているのも確認したんだぜ。つまり、ギルバードがメンバーに提案して……エリスに本を取りに行かせる。そうすれば本棚の間に彼女は来るだろ? そこでタイミングを見計らって、少し開いたガラスの扉からロープを引っ張る。すると、一番奥の本棚が前に倒れてドミノ倒しになり……エリスを下敷きにできる。そこからはロープを引っ張って回収して何事も無かったかのように図書室に戻るんだ」
ゴルゴの推理を整理してみた。
きっとエリスと同じグループになったギルバードはメンバーに「この調べ学習をするなら、最適な本がある」とある一冊を紹介した。それをメンバーは書き記した。
ギルバードはそれからエリスに本を取りに行かせる。作者の頭文字は「J」だ。
しかし、「J」から始まる作者の本はそこにはなく、困惑するだろう。
時を同じくしてギルバードは外に出てロープを引いて、本棚を倒れさせる。そして、ロープを回収する……。これが全ての推理のはずだ。
「間違いねえのはよ、ギルバード、お前の持ち物からその『ロープ』が出てくることだがよう。それは警察に任せるとするぜ。さあ、どうする? 言い逃れができるならしてみろ」
両手を広げて挑発するようなゴルゴの言葉に、ギルバードは無言のまま彼を見据えていた。
本当に犯人はギルバードなのか。
ここまで犯行を指摘されて、次の一秒後には彼が自供を始めるかもしれない。そう考えるとニッキーは固唾を飲んで状況を見定めようと、すっかり二人の間に漂う空気を全身で感じ始めた。
誰も何も話さない時間が流れていった。
ふと、ニッキーはギルバードの顔つきを見て、あることに気がついていた。
彼の顔から感じられるのは「言い逃れをしようとする犯人」のものでも「無実を証明しようとする一般人」のものでもなかった。
眉間の皺を深くして思考するのはこの事件の真相のような気さえさせてくれる。
ギルバードはゴルゴの描いたのとは違う結末を導こうとしているようだったのだ。
場を収めるべき言葉を誰も持ってはいなかった。
そこでニッキーは誰かが階段を上がってくる音を聞くのだった。
当直の教師に違いない。きっと、深夜の校舎の巡回に来たのだ。ところがその足音はこの場の皆に届いているはずなのに、誰も動き出す気配がなかった。
慌ててニッキーは全員に教師の接近を知らせ、半ば無理矢理、皆を図書室から追い出すと元のように鍵をかける。
そして、ライトを照らしながら歩いてくる教師とは逆の方へと逃れていくのだった。
元来た道を通って校舎の外に出ると、ゴルゴはギルバードに告げる。
「どうだ? 自首する気になったか?」
「しないと言ったらどうするんだ。この場ですぐに俺を通報するか?」
返す言葉に全くの弱さはなかった。通報できるわけがないとギルバードは読んでいるかのようにさえ感じられるのだった。その強気な態度の理由がニッキーには分からない。
「通報してやるぜ。こいつがエリスを殺したって言ってやる。証拠だって揃ってるんだからな」
まるで喧嘩でも始めようかというようなラルフの言葉を、ギルバードは一度睨み付けるだけで返事をしなかった。
「本当にそれで良いのか。この場には迷っている者もいるだろう。その理由を突き詰めていった結果、俺を通報するのならばそれはそれでいい。だが、真実はゴルゴの語られたとおりとは限らないと思うがな」
ギルバードは思わせぶりに言う。
そして、この場で彼を通報しようということに迷いを持っているのはニッキーであった。
確かにゴルゴの示した証拠や証言は全てギルバードを犯人だと示している。
しかしながら、決定的なものがまだ不足しているように感じていた。
それだけではない。
ゴルゴやラルフが生み出した推理には「どこか穴がある」ようにも思えるのだった。
一度鑑賞した映画を頭の中で再生して大切なシーンを拾い集める、ということをニッキーはよく行っていた。
それを同じ要領で、ギルバードを疑い始めてからこの夜までの出来事を思い返して、重大な場面を再び頭の中で再生してみた。
ギルバードが州立大学への給費生に繰り上げで合格したこと。
エリスが給費生だと彼が知ったきっかけについて。
そして、実際にエリスを手にかけたこと。事故に見せかけた殺人の方法について。それらを指摘したゴルゴやラルフの推理について。
全ての謎が絡み合ってニッキーの中で一つの選択を迫ろうとしていた。
本当にギルバードが犯人なのか?
それが誤っているとしたら、一体誰がエリスを殺したのだろうか?
続く